美術展のおこぼれ 6
「駒井哲郎1920-1976」
会期:2011年4月9日―6月12日(第I部4月9日―5月8日、第II部5月11日―6月12日)
会場:町田市立国際版画美術館
福原義春コレクションからの約500点を2回に分け年代順に構成した展示である。その前半部を見ていくなかで、自分の記憶では1948年から51年の代表作を一挙に紹介した「みづゑ」の特集号を兄が買ってきて、それを見たときの衝撃以来、美術誌などで知るかぎりの駒井哲郎の仕事をずっと追って見て来た、そのおさらいをしている気持ちになった。
上記の時期の、たとえば《束の間の幻影》は自分の眼の裏側にあったもの、《夜の魚―夢》や《地下室(ヴィラ・メイズの地下部屋)》は夜ごとの夢、つまりは「見る」ことのありえない光景が、ふいに外化され作品というものになっていることへの驚きは、それが別のイメージに託されることなく「直接に」描かれていたからである。だからそこに絵としての定まった構図はない。《束の間・・・》はまさしくそうだし、《夜の魚》も急に近づいてきて鼻づらと鱗を一瞬光らせ、また暗い海底に去っていくあわいの知覚であるし、《地下室》も果てしのない闇のなかで辛うじて照らし出された(しかもそのときは天井や壁に隠された配管まで見える)建築の一隅でしかない。この魚や部屋は前から外にあった形象ではないのだ。
銅版画という、たぶん当時は知らなかった技法(その1、2年前の中学の図工の時間で多色刷り木版にはけっこう夢中になっていたくせに)に魅せられたのは当然だが、それについてはあとで触れることにして、その後の駒井を追いつづけた関心の第一は、直接的なイメージを直接的なままにどう展開していくのか、それに尽きていたと思う。しかしその後は、樹木、鳥や魚、平原や岩礁、卓上の静物といったイメージに、でなければ抽象的な攪拌するイメージなどに幻影や夢が託されていく。さらにはメリヨン、ルドン、クレーをはじめ多くの画家の作風を下敷きにした作品まで登場する。これらの仕事においても比類ない精度は変わることはないが、なにか外の形象に託す試み、既成の画家のスタイルを次々ととりいれる過渡的な試みといった印象もつきまとう。そしてこれらの仕事が、《からんどりえ》や《人それを呼んで反歌という》の詩画集に代表される、品がよくやや抒情的であり、抽象化に向かうことで完成度を高める方向と、《マルドロオルの歌》や《闇のなかの黒い馬》の挿図における、不気味でグロテスクなものへの傾斜をもち、具象に向かうことでイメージが強化される方向をも見せられると、「直接的なイメージ」の行方を定められなくなってしまう。
あるいはこうした試行は、1948-51年の時点で描き切ったとする「幻影」や「夢」、あるいは内面的といった言葉で尽くされてしまいがちな作品からの脱却だったのか。しかし直接性からは遠ざかる。駒井にたいしてだけはそんな無いものねだりをしつづけていたような気がする。
私個人はどちらかといえば、不気味さに向かう作品が好きなのだが、そこに直接性を重ねると1960年の《Fou(阿呆)》と62年の《poisson ou poison(魚または毒)》の2点が残る。抽象でも具象でもない。「そのもの」が眼の前にあることの懼れ。こんなものまでもっともシンプルなかたちで描いてしまえることにこそ、この銅版画家の紛れもない力量を確信するのだが、それは「幻影」や「夢」の発展型なのか、それとも目覚めて陽光の下で見た残片であるのか。48-51年期にはもう1点、見逃せない作品がある。綿貫さんによれば、福原氏がコレクションのなかでもとくに愛着をもっておられるという、1950年の《ラジオ アクティヴィティ イン マイルーム》で、ドアらしきものが見えるだけの空っぽの部屋の奥から何かがこちらに向けて激しく放射されている(ラジオの音? それとも?)。容赦なき単純直接な絵で、部屋とあきらかに見える外形が逆に不安の輝きに満たされ、幻影であり夢になっていく。この辺からすでに駒井の直接性は多岐に始まっていたのだろうか。
「銅版画のマチエール」がつねに先ずあり、とにかく銅版に触っていなければ何も生み出せないといった言いかたで「物質」を規定した駒井を考えると、直接的なイメージ、つまり見えない対象の写実主義を彼の作品に求めつづけるのは決して不毛ではないと思えてくる。それはたとえば、エルンストがコラージュやフロッタージュの発見によっていきなりイメージの沃野に踏みこんだのとも違っていて、まず銅版を刻みはじめる行為は、ばあいによっては表現の極貧にまで立ち会いながら、その先をさらに追いつづける持続を可能にしたのではなかったか。駒井は、長谷川潔や浜口陽三、あるいはより若い世代の銅版画家のように明快で生涯的なスタイルを持つことはなかった、と私は思うのだが、にもかかわらず、彼のすべての作品は誰にもまして画家のアイデンティティを証しているのだ。
直接性と繰り返しながら自分でも説明できていない。別の言いかたをすれば、限りなく古い記憶に戻っていくこと。それ以外のすべてが消え、意味を失うレベルにまで。
駒井の銅版画に出会って以来、60年間(なんと!)に無意識のうちにつくってきた、いわば私的な空想画廊の様子を初めて文字にしてみると何んだかヘンだ。今回あらためてその現実の作品を見渡して思うのは、駒井は世界のあらゆる形象について、また関心をもつすべての銅版画作家について、その「幻影」と「夢」の強度を、自分のスタイルなど顧慮することなく銅版を刻みつづけることで、検証しつづけたのではないか。その尨大な作業の記録が結果として残されたのではないか。そういった思いもかけないスケールが、この美術館で、駒井の仕事を回顧できる時期にこそ発生しつつあるのかもしれない。常設展示室では同じ期間にあわせて「西洋版画の世界―駒井哲郎の視点」展が開かれている。画家の名や技法の知識を知ることだけに終らなければ、駒井の残したものをより大きく見直すためのよい助けになりそうだ。
(2011.4.11 うえだまこと)
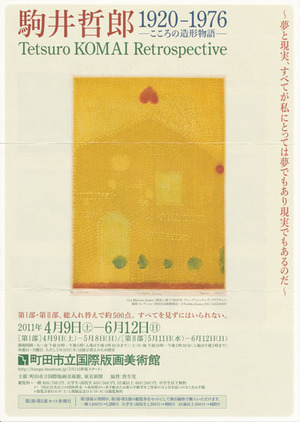

「駒井哲郎1920-1976」
会期:2011年4月9日―6月12日(第I部4月9日―5月8日、第II部5月11日―6月12日)
会場:町田市立国際版画美術館
福原義春コレクションからの約500点を2回に分け年代順に構成した展示である。その前半部を見ていくなかで、自分の記憶では1948年から51年の代表作を一挙に紹介した「みづゑ」の特集号を兄が買ってきて、それを見たときの衝撃以来、美術誌などで知るかぎりの駒井哲郎の仕事をずっと追って見て来た、そのおさらいをしている気持ちになった。
上記の時期の、たとえば《束の間の幻影》は自分の眼の裏側にあったもの、《夜の魚―夢》や《地下室(ヴィラ・メイズの地下部屋)》は夜ごとの夢、つまりは「見る」ことのありえない光景が、ふいに外化され作品というものになっていることへの驚きは、それが別のイメージに託されることなく「直接に」描かれていたからである。だからそこに絵としての定まった構図はない。《束の間・・・》はまさしくそうだし、《夜の魚》も急に近づいてきて鼻づらと鱗を一瞬光らせ、また暗い海底に去っていくあわいの知覚であるし、《地下室》も果てしのない闇のなかで辛うじて照らし出された(しかもそのときは天井や壁に隠された配管まで見える)建築の一隅でしかない。この魚や部屋は前から外にあった形象ではないのだ。
銅版画という、たぶん当時は知らなかった技法(その1、2年前の中学の図工の時間で多色刷り木版にはけっこう夢中になっていたくせに)に魅せられたのは当然だが、それについてはあとで触れることにして、その後の駒井を追いつづけた関心の第一は、直接的なイメージを直接的なままにどう展開していくのか、それに尽きていたと思う。しかしその後は、樹木、鳥や魚、平原や岩礁、卓上の静物といったイメージに、でなければ抽象的な攪拌するイメージなどに幻影や夢が託されていく。さらにはメリヨン、ルドン、クレーをはじめ多くの画家の作風を下敷きにした作品まで登場する。これらの仕事においても比類ない精度は変わることはないが、なにか外の形象に託す試み、既成の画家のスタイルを次々ととりいれる過渡的な試みといった印象もつきまとう。そしてこれらの仕事が、《からんどりえ》や《人それを呼んで反歌という》の詩画集に代表される、品がよくやや抒情的であり、抽象化に向かうことで完成度を高める方向と、《マルドロオルの歌》や《闇のなかの黒い馬》の挿図における、不気味でグロテスクなものへの傾斜をもち、具象に向かうことでイメージが強化される方向をも見せられると、「直接的なイメージ」の行方を定められなくなってしまう。
あるいはこうした試行は、1948-51年の時点で描き切ったとする「幻影」や「夢」、あるいは内面的といった言葉で尽くされてしまいがちな作品からの脱却だったのか。しかし直接性からは遠ざかる。駒井にたいしてだけはそんな無いものねだりをしつづけていたような気がする。
私個人はどちらかといえば、不気味さに向かう作品が好きなのだが、そこに直接性を重ねると1960年の《Fou(阿呆)》と62年の《poisson ou poison(魚または毒)》の2点が残る。抽象でも具象でもない。「そのもの」が眼の前にあることの懼れ。こんなものまでもっともシンプルなかたちで描いてしまえることにこそ、この銅版画家の紛れもない力量を確信するのだが、それは「幻影」や「夢」の発展型なのか、それとも目覚めて陽光の下で見た残片であるのか。48-51年期にはもう1点、見逃せない作品がある。綿貫さんによれば、福原氏がコレクションのなかでもとくに愛着をもっておられるという、1950年の《ラジオ アクティヴィティ イン マイルーム》で、ドアらしきものが見えるだけの空っぽの部屋の奥から何かがこちらに向けて激しく放射されている(ラジオの音? それとも?)。容赦なき単純直接な絵で、部屋とあきらかに見える外形が逆に不安の輝きに満たされ、幻影であり夢になっていく。この辺からすでに駒井の直接性は多岐に始まっていたのだろうか。
「銅版画のマチエール」がつねに先ずあり、とにかく銅版に触っていなければ何も生み出せないといった言いかたで「物質」を規定した駒井を考えると、直接的なイメージ、つまり見えない対象の写実主義を彼の作品に求めつづけるのは決して不毛ではないと思えてくる。それはたとえば、エルンストがコラージュやフロッタージュの発見によっていきなりイメージの沃野に踏みこんだのとも違っていて、まず銅版を刻みはじめる行為は、ばあいによっては表現の極貧にまで立ち会いながら、その先をさらに追いつづける持続を可能にしたのではなかったか。駒井は、長谷川潔や浜口陽三、あるいはより若い世代の銅版画家のように明快で生涯的なスタイルを持つことはなかった、と私は思うのだが、にもかかわらず、彼のすべての作品は誰にもまして画家のアイデンティティを証しているのだ。
直接性と繰り返しながら自分でも説明できていない。別の言いかたをすれば、限りなく古い記憶に戻っていくこと。それ以外のすべてが消え、意味を失うレベルにまで。
駒井の銅版画に出会って以来、60年間(なんと!)に無意識のうちにつくってきた、いわば私的な空想画廊の様子を初めて文字にしてみると何んだかヘンだ。今回あらためてその現実の作品を見渡して思うのは、駒井は世界のあらゆる形象について、また関心をもつすべての銅版画作家について、その「幻影」と「夢」の強度を、自分のスタイルなど顧慮することなく銅版を刻みつづけることで、検証しつづけたのではないか。その尨大な作業の記録が結果として残されたのではないか。そういった思いもかけないスケールが、この美術館で、駒井の仕事を回顧できる時期にこそ発生しつつあるのかもしれない。常設展示室では同じ期間にあわせて「西洋版画の世界―駒井哲郎の視点」展が開かれている。画家の名や技法の知識を知ることだけに終らなければ、駒井の残したものをより大きく見直すためのよい助けになりそうだ。
(2011.4.11 うえだまこと)
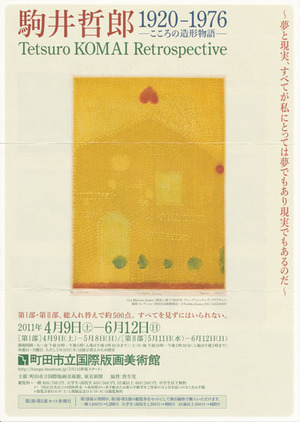

コメント