生をうつす旅という回路
平嶋彰彦
(西村多美子写真集『憧景』より再録)
本書は西村多美子の血の轍ともいうべき若き日の旅の記録である。
写真の日付は1970年から83年ごろというから、作者が20代から30代だったときにうつしたものである。撮影地は北海道・東北が大半をしめているが、関東・北陸・関西と広範囲にもおよんでいて、なかには地元の東京でうつしたものもふくまれている。
1970年といえば、連合赤軍による日航機よど号のハイジャック、日米安全保障条約をめぐる全国的な反対行動、大阪で開催された万国博覧会、あるいは三島由紀夫の市ヶ谷自衛隊駐屯地における割腹自殺などの事件がおもいだされるが、旧国鉄のキャンペーン「ディスカバー・ジャパン」がはじまったのもこの年である。
このキャンペーンは個人旅行者や女性旅行客の拡大をはかったもので、新聞・雑誌メディアをつうじて喧伝されたばかりでなく、旧国鉄がスポンサーになり「遠くへ行きたい」の題名でTV番組まで製作された。山口百恵の「いい日旅立ち」(谷村新司作詞・作曲)は1978年のヒット曲だが、もともとは「ディスカバー・ジャパン」のテーマ曲としてつくられている。
北海道の倶知安駅で列車の窓からうつした夏の羊蹄山の写真がある(30-31ページ)。
 「倶知安、北海道」
「倶知安、北海道」
プラットホームのむかいに停車しているのは9615型の蒸気機関車である。機関車に作者の興味はなかったかもしれないが、運転手は好奇の目でカメラを見つめている。ふりかえってみれば、このころまではまだ女の一人旅はめずらしかったのである。
「あるくみるきく」は民俗学者の宮本常一*が主宰した月刊の旅雑誌としてしられる。スポンサーは近畿日本ツーリストで、創刊されたのは1967年である。雑誌名の「あるくみるきく」は宮本の旅の思想を要約したもので、「旅にまなぶ」(「宮本常一著作集31」所載)にはつぎのような趣旨の文章がつづられている。
<旅をするのはなにかを発見するためである。それには歩いてものを見てみるしか方法はない。ものを見ていくと、わからないことが増えてくるが、わからないことを確かめて、明らかにするところに、旅の目的がある。>
宮本常一を引き合いにだしたのは、わからないことを確かめて、明らかにするという宮本の旅の思想と作者の写真の面構えにどこか通いあうものを感じるからである。もとより作者の写真紀行は「ディスカバー・ジャパン」の観光旅行でもなければ、民俗採訪の学術調査ともちがっている。どちらかといえば前代までの物見遊山や霊地巡礼といった庶民信仰の旅によほどちかく、そういってよければ芭蕉*の俳諧紀行をほうふつさせるものである。
芭蕉の紀行文集「野ざらし紀行」は旅を死出の道行にたとえたものである。死出の道行とはいっても、実際はあの世への片道切符でないわけだから、旅立ちのときの「野ざらしを心に風のしむ身かな」のおもいつめた心境は、旅の途中で「死にもせぬ旅寝の果よ秋の暮」と諧謔的によみなおされている。野ざらしとは野にさらされて白骨化したサレコウベのことである。芭蕉は野ざらしとなることを旅の理想にしているわけだが、そこには風狂の戯れ言としてかたづけられない、古代からの民俗的な死生観がうもれている。
8世紀に編纂された「古事記」と「日本書紀」に旅の記述がでてくる。イザナギが死んだ妻のイザナミを黄泉国にたずねる神話でも、アマテラスの神田を汚すなどの罪をおかしたスサノヲが根の国に追放される神話でも、旅するものは神であり、その行き先はあの世である。いずれも死の世界をめぐることにより、神が誕生するとか復活するとかいう物語構造になっていることは見のがせない。
「日本書紀」の一書によれば、スサノヲは青草を結いたばねた笠蓑をまとっていたが、これを目にした八百万の神々は誰ひとりとして宿をかさなかった。笠蓑は雨つゆにぬれるのをふせぐ道具というよりも、死者が身につける死装束の象徴であった。筆者の郷里は房総半島の南部であるが、このあたりでは死者の命日をタチビ(立ち日)、遺骸を埋葬する場所をタチバ(立ち場)または訛ってタチューバとむかしから呼んできた。タツ(立つ)とはあの世への旅立つことをさしてそういうのである。
芭蕉は「奥の細道」の序章で、どうして旅をするのかを自問自答したあげく、「片雲の風にさそわれて、漂泊の思ひやまず」とも「そヾろ神の物につきて心をくるはせ、道祖神のまねきにあひて取るもの手につかず」ともかいている。旅に出ようとする発心は主体的な意識であるにもかかわらず、自分では手におえないなにものかであり、始末のわるいやっかいなしろものだというのである。その観点からすれば、旅の世界は生死や性愛の問題とよくにている。
上記の文中にある「そヾろ神」は芭蕉の造語だとおもわれるが、東北地方の旧家にはオシンメイサマともオシラサマ・オクナイサマともよばれる正体不明の神をまつる風習があったことを、柳田國男*が「大白神考」(「定本柳田國男12」所載)にかきとめている。
「オシンメイサマを持ち伝えた旧家の主婦は、夢にしばしば神の催促を聴き、一年に一度はこの木像を背に負うて、立ち出でゝあるきまわらぬとぶらぶら病にかゝる」
主婦たちをそそのかしたというその木像をカメラに置きかえてみればわかりやすい。西村多美子という写真家は、正体不明の神に心を狂わせて漂泊の旅にでたといわれるこの忘れられた女たちの後裔であるようにおもわれてならない。
うつす(写す)という語を白川静*の「字訓」でひいてみると、本来のものを他に移して、その色や形を再現することである、とかいてある。写すは他動詞である。写すは模すにつうじる。
写すことは見るという知覚行動をふまえている。見るという言葉は目と同根で、目にとめて見る、その機能をいう、とも白川静はかいている。日本語の見るは、たんにものを眺めることをさししめすだけでないということだ。ものを観察する・知る・判断する・世話をするなど多義的な意味をふくんでいるのである。古くは男女が契ることまでも見るといったらしい。男と女がものを隔てずにあうことは夫婦関係にはいることに解されたともいわれている(「新潮国語辞典」)。
本書にはカメラをじっくり構えてとったとおもわれるような写真はまずみあたらない。出会いがしらにそっけなくうつしとったものばかりである。対象が人物であっても事物であってもそれは変わらない。安定した構図、正確な露出や測距は二の次になっている。目にとまるとか気にかかるものがあれば、なんであってもかまわない、ぐずぐずしないで、とっさにうつしとろうとする姿勢がはっきりとうかがえる。
西村多美子の写真につらぬかれている方法論には、うつすという作者の主体的なはたらきかけよりも、目標物はおのずからうつってくるものであるという一種共犯的な期待と他力本願的な確信があるようにおもわれる。ものを見るとか見られたりするのは相手があってのことで、見るという知覚行動は相手から触発されることがなければ成立しない。見ることと見られることは相互規定的なきわどい関係にある。誤解をおそれずにいえば、西村の写真はものをうつすというよりも、ものが憑くという印象を強くうける。憑くというのは、ものがのり移って憑りつくことをいうのである。
場当たり的とも刹那的ともいえる撮影方法とは対照的に、プリント作業には神経質なくらいたっぷりと時間と手間をかけている。砂をまぶしたような銀粒子のあれた画面をみれば、高温か長時間かはともかく、常識はずれなフィルム現像をしているのは想像にかたくない。しかし手間ひまのかかるのはそのせいばかりではないだろう。コントラストを強調した奥行のふかい白黒の色調や手のこんだ焼き込みと覆い焼きは、日本語の見るという言葉における観察する・知る・判断するという知覚行動の試行錯誤を示唆している。
巻末に掲載された撮影地の一覧をみると、どこもいわくや因縁があって馴染みのある地名ばかりがならんでいる。あいつぐ炭鉱の閉山でゆれる北海道の夕張*や、かつて米軍試射場反対闘争*のあった石川県の内灘など、戦後史にのこる著名な社会的事件や住民闘争のあった町にも足をはこんでいる。旅にさいして芭蕉の俳諧紀行における枕詞に類する目あてのようなものが作者にもあったはずであるが、地名を喚起させる象徴性をもつ事物や事象をうつしこんだ写真はわずかしかみあたらない。あたりまえのようにどこにもありふれている場面ばかりなのだが、どういうわけか写真を見はじめると目が離せなくなる。
一例をあげれば、北海道の旭川でバラック風の建物が軒をつらねる場末の繁華街をとった写真がある(18-19ページ)。

「旭川、北海道」
大通りには雪が凍てついたまま残っている。歩道に目をやると、こちらにむかって歩いてくる手さげ袋をもち足元はゴム長靴の女。すぐ後ろに、耳あて帽子をかぶった母親と幼児の二人連れ。いちばん手前の家では玄関のガラス戸を半開きにし、やはり親子とおもわれる女と少年が通りをながめている。少年はトックリのセーターにカーディガン姿。軒先には自転車がならべられ、古風な木製の脚立がたてかけてある。
よくみると、少年はあおぐように視線をカメラにそそいでいる。カメラの位置はそれよりも高い。どうやら作者はバスの車窓からうつしているらしい。通りすがりの旅行者に通りすがりの人たちが目にとまり、交差点をバスが曲がるつかの間に名前のないいくつもの人生がすれちがう場面である。ありふれた偶然が目をみはらせる情景になっている。地味な画面構成でうっかり見過ごしかねない写真だが、絵解きをすればそんなことになる。ものを見てからカメラを構えるのではまにあわない。見ることとうつすことが切れ目のない連続行為として意識されていなかったら、こんなふうにものはうつってこない。
作者はバスばかりでなく移動中の列車のなかや船のうえからも写真をとっている。なかにはホテルの部屋からとったとみられるものもある。大半は歩いてとった写真であるが、立ち止まらずに歩きながらカメラをむけているようにおもわれる。それは眼差しをそそぐのがつかの間の瞬間であるという作者の心構えをしめしている。男女の関係にかぎらない。見ず知らずの相手を理由もなくじろじろと見ていたらただですまなくなるのは、今も昔もかわりはしない。自由にものを見ることが許されるのは、つかの間という制限された時間でしかないのだ。見ないということが人間社会の安全装置になっていることに私たちはもっと注目していいのではないだろうか。
この写真集の題名を作者は「憧景」と名づけている。前作の「実存」(2011年、グラフィカ編集室)は唐十郎*の状況劇場を1968-69年に取材したものである。芝居小屋が近代以前に悪所とよばれたのは、そこが無縁・公界の非日常的な世界とみなされたからである。旅とは家をはなれることで、日常的な時空間からの離脱もしくは追放を意味する。旅も芝居も無縁・公界の非日常的な世界に帰属する。芝居役者が発生史的に道々の者であったことをかんがえれば、仮そめとはいえ座付き写真家を体験した作者が旅に転位をもとめたことは驚くにあたらない。「憧景」とは具象化された「実存」をさしている。
本書のあとがきで、作者は結界をこえることに言及している。旅をするとは越境することで、結界をこえることにほかならない。村境や国境は同時にこの世とあの世を分かつ場所でもあった。だから注連縄をはるとか、塞の神や道祖神をまつったりしたのである。さきにのべたスサノヲの神話にみられるように、わが国の古い民俗では、旅をするものは死者か神仏のいずれかに見立てられた。芭蕉は野ざらしのサレコウベとなることを旅の理想としている。物見遊山や霊地巡礼は、いったん死んだことにし、あの世をめぐりあるき、ふたたびこの世によみがえる、という擬死再生の庶民信仰であった。芭蕉の「死にもせぬ旅寝の果よ秋の暮」の句は、風狂の俳諧紀行もまたそうした歴史的習俗をふまえたものであったことをものがたっている。
旅をするのは、死者の眼差しをもってあの世からこの世を見るためである。死者の関心は、わが身の不在によって生き残った人たちが苦労を強いられないかどうかにある。作者は目にとまり胸騒ぎを感じれば、何であろうとかまわずうつしている。胸騒ぎをおぼえるのはなにか現実的な理由があるからである。写真は来しかた行くすえの定まらないわが身と現実世界の在り方をさぐりだす糸口でもある。写真にうつされたものは夢の断片とおなじで脈略がないようにみえるが、作者が見ようとしてうつした現実であることは否定のしようがない。西郷信綱*によれば、夢が現実と対比されるのは後世になってからのはなしで、古代までさかのぼれば、夢は現実に見るもので、現実を写すものであったということである(「古代人と夢」)。
ふと、若い母親が赤ん坊を背負った写真に目がとまる。赤ん坊をねんねこ半纏で背中にくるまなくなったのはいつごろからだろうか。1人だけではない。作者はおなじような母親をくりかえしうつしている。そういえば、この写真集では女と子どもばかりに目がむけられていることに気づく。7歳までは神のうちで、子どもは男も女もないが、おとなの男となるとは数えるほどしか登場しないのだ。それも女と2人連れで、男だけが大きくうつっているのは1枚もない。その女といえばだれもかれも黙々として名前のない表情をしている。そうでなければ後姿であるか、影にかくれて表情がみえない。それをくいいるように見つめている作者の姿がおのずと目に浮かんでくる。
作者の西村多美子は1948年生まれで、72年に結婚し74年に出産を体験しているという。それぐらいのことしか知らないのだが、知らなくともいっこうにかまわない。写真をたどっていけば、旅のなかで目にとまった女たちの生きる姿とはまぎれもなくもう1人の西村多美子であったことが浮き彫りになってくる。
(ひらしまあきひこ)
*脚註
宮本常一 みやもとつねいち(1907-1981)
民俗学者 山口県周防大島生まれ
戦前より日本全国をめぐり歩き、膨大な民俗の記録を残した。
著書『忘れられた日本人』、『庶民の発見』、『私の日本地図』 全15巻。
没後に出版された書籍『宮本常一写真・日記集成』(上下巻+別巻)2005
松尾芭蕉 まつおばしょう(1644-1694)
江戸前期の俳諧師 伊賀国(現三重県)生まれ
『野ざらし紀行』は、1684年に江戸から故郷の伊賀上野への旅を中心に、句と文をあわせて記した紀行文。『おくのほそ道』は1689年に江戸を出て、東北、北陸を巡り大垣までの旅をやはり俳句と文を合わせて綴った紀行文。
柳田國男 やなぎだくにお(1875-1962)
民俗学者 兵庫県生まれ
日本民俗学の黎明期を担ったもっとも著名な一人。東大で農政学を学び、農務官僚となる。全国への視察や新渡戸稲造との交流などを契機に、各地の民間の習俗、信仰への関心を大きくする。1913年雑誌『郷土研究』刊行。
著書『遠野物語』、『蝸牛考』、『海上の道』
白川静 しらかわしずか(1910-2006)
中国文学者 福井県福井市生まれ
古代中国文学、漢字の研究者。漢字の発生と変化を、人と世界との交流による啓示と応答の表象として読み解く、深遠な漢字世界の研究を遺した。
著書『字統』、『字訓』、『字通』(辞書)『漢字の世界1、2』『漢字』、『中国古代の民俗』
北海道夕張市
明治初期にドイツ人技師ライマンが石炭鉱脈の可能性を指摘したことで調査が始まり、明治中期から次々に炭鉱がひらかれた。北海道炭礦汽船(通称・北炭)が夕張地域で最大の事業主。他に三菱鉱業による大夕張炭鉱など。戦後、1960年頃の最盛期のあと、エネルギー政策の石油への転換、大規模な事故などにより、1970年代前半より閉山が進む。
80年代に観光による振興を目指し、ジェットコースターや観覧車まで作られ、モデル自治体として当時の政府から表彰されるが、破綻。2007年に財政再建団体となる。
米軍試射場反対闘争(内灘闘争)1952-57
石川県河北郡内灘村の海岸砂丘を朝鮮戦争で使用する砲弾の試射場として米軍が接収したことに反対した村民の抵抗活動に、学生をはじめ全国から労働組合団体などが加わり、戦後の米軍基地反対闘争の口火となった。
唐十郎 からじゅうろう(1940- )
劇作家、俳優 東京都生まれ
明治大学文学部演劇学科卒業後、「シチュエーションの会」を立ち上げ、後に「状況劇場」と改名する。60年代末期からのアンダーグラウンドの時代に、寺山修司の「天井桟敷」などと共に中心的存在だった。新宿の花園神社をはじめ、様々な場所に紅テントを設営し公演を行った。俳優陣は、初期は、麿赤児、四谷シモン、李礼仙、藤原マキ、大久保鷹、不破万作など。その後も根津甚八、小林薫、佐野史郎、金守珍などの個性の強い役者が揃っていた。
代表作『腰巻きお仙・義理人情いろはにほへと篇』『ジョン・シルバー』、『少女仮面』(早稲田小劇場)。戯曲以外の著書 『特権的肉体論』 、『佐川君からの手紙』、『海星・河童-少年小説』
西郷信綱 さいごうのぶつな(1916-2008)
国文学者 大分県生まれ
戦後における古代文学研究の第一人者。歴史学、民俗学など他の学問分野の観点を積極的に取り入れ、国文学研究に新しい地平を切り開いた。著書 『貴族文学としての万葉集』 、『古事記の世界』、『古代人と夢』 、『古事記注釈』『梁塵秘抄』 、『斎藤茂吉』
*脚註文責:グラフィカ編集室
-----------------------------
Reflect Forward: the Journey is the Route
Akihiko HIRASHIMA
This book, we might say, traces the pulse of Nishimura Tamiko's youth on the road. The images were shot between her 20s and 30s – from around 1970 to 1983. Most were taken on the northern island of Hokkaido and through the northeastern Tohoku area, but also across the Kanto (including her hometown Tokyo), Hokuriku and Kansai regions.
Nineteen-seventy was an eventful year for Japan. There was the Red Army hijacking of a JAL passenger plane, massive nationwide protests against the US-Japan "AMPO" security treaty, Osaka Expo '70, and Mishima Yukio's seppuku suicide at the Japan Self-Defense Force Barracks in Ichigaya. The same year saw the launch of the now-privatised Japan National Railway's "Discover Japan" campaign, targeting prospective solo and women travellers. JNR even sponsored a regular TV programme, Touku e Ikitai ("I Want to Travel Far").
In the photograph of Mt. Yotei (pp.30–31), taken from a train window at Kutchan Station in Hokkaido, we see a steam locomotive across the tracks. The train may not have interested Nishimura at the time, though her camera is attracting attention, as the driver is peering at it curiously. Solitary women travellers were obviously still a rarity then.
The title of folklorist Miyamoto Tsuneichi's monthly magazine Aruku Miru Kiku ("Roam, See, Hear"), sponsored by the Kinki Nihon Tourist agency and first published in 1967, sums up his travel philosophy. In the article Tabi ni Manabu ("Learn by Travelling"), he says: "We travel in order to discover things. There really is no other way than to go see for yourself. The number of unknowns may increase when we go see things. Another reason to travel is to verify and clarify the unknown."
Whatever similarities we may sense between Miyamoto's thinking and Nishimura's photographic forays, her travels were neither Discover Japan tours nor folklore surveys. If anything, they were closer to folk pilgrimages of a bygone era, to places haloed and spiritual. The sort of personal quest that sent the poet Basho on his haiku wanderings.
In Nozarashi Kiko ("Bare Bones Travelogue"), Basho likens travel to the "way to death." Basho's ideal of faring on and on, until reduced to bones, cannot be dismissed as the mere musings of an eccentric. It underscores a Japanese view of life and death that has been popular since ancient times.
Travel also figures in the 7th century Kojiki ("Record of Ancient Matters") and 8th century Nihon Shoki ("Chronicles of Japan") imperial codices. For example, the descent by ancient deity Izanagi into the Underworld (Yomi) in search of his deceased wife Izanami. Nihon Shoki shows the sun goddess Amaterasu banishing her brother, the storm god Susano-o, to the Root World (Ne no Kuni), for defiling the sacred rice fields. Both are mythic journeys leading to divine rebirth.
In his preface to Oku no Hosomichi ("Narrow Path to the Far North") Basho asks himself why he travels: "A lone cloud blown about in the wind cannot but imagine itself adrift," he writes. "Driven to distraction by things divine, the ancestral guardians of the road beckon toward what lies ever out of reach." While the impetus to set forth may be a conscious subjective choice, the prospect literally gets out of hand and ends up being a curse. In that sense, traveling is as unpredictably fraught as life and death – or love and sex.
The pioneering folklore scholar, Yanagida Kunio, notes in his article Oshiragami Ko that old households in Tohoku customarily practised observances related to a mysterious spirit known as Oshinmei-sama, Oshira-sama or Okunai-sama. "Matrons of these families who subscribe to the Oshinmei-sama cult frequently hear divine promptings in dreams," he writes, "and will incur serious illnesses should they not to go walkabout, shouldering his wooden statue, once a year." Exchange the onerous wooden image for a camera, and it is not difficult to see our photographer Nishimura as a latter-day scion of those forgotten women, who set off wandering possessed by a mysterious spirit.
The Japanese transitive verb utsusu, which can mean "to photograph", originally meant "to move things from one place to another." It since came to include such notions as reproducing colour and form, hence copying or emulating. It implies the perceptual act of seeing. Likewise, the verb miru (見る) "to see" stems from the Chinese character me (目), "eye" – that is, the function of fixing one's eyes upon something. Thus, "to see" in Japanese refers not only to gazing, but covers a broad range of meanings from observing, knowing, judging, and even caring. In olden times, it seems that male-female relations were also a kind of "seeing."
None of the photos in this book are very studiously composed, whether the subjects are people or things. Steady composition, correct exposure and focal range are secondary. Rather, what clearly comes across is Nishimura's straightforward stance toward shooting whatever caught her eye, without hesitation or undue posturing.
Her photographic method is less that of an artist subjectively seeking to capture an image than of letting the target object show itself. She joins in a kind of conspiratorial expectation, or belief in salvation by "other powers". Thus seeing and being seen are mutual, the perceptual act of seeing must be inspired by the other; the relationship of the seer to the seen prescribes a tenuous reciprocity.
Counter to the happenstance ephemerality of photo-graphing, however, the act of printing requires assiduous, time-consuming effort. To look at the silver-particle sandstorms of Nishimura's grainy images, we can easily imagine she developed her films using high temperatures or long bath times, or other unorthodox methods. The deep blacks and high-contrast whites, the laborious hand-shading techniques, attest to considerable trial and error.
Nishimura must have had her benchmarks, not unlike the makura-kotoba set-phrases of Basho's haiku travelogues. But very few of the events and things shown in her photos speak of specific locales. Most are of commonplace scenes and yet their evocative power captivates us.
The image of the shack-like facades of a rundown street in Asahikawa, Hokkaido (pp.18-19), for instance, shows the icy remnants of snow in the gutter by a footpath where walks a woman in gumboots with a carrier bag. Right behind her is a mother in an ear-muffed hat with her child. The glass door to the closest house is half-open, revealing what seems to be a mother with her son in a turtleneck and cardigan, looking out on the street. A row of bicycles lines the street and an old wooden ladder leans up against some eaves. Look carefully and you notice the camera is peering directly at the boy from a slightly elevated position. Perhaps Nishimura took this from a bus window. These unnamed people going about their everyday lives must have caught her eye just as the bus turned at an intersection. A chance glimpse that makes us see the poetry in the everyday. The composition is so understated as to be easily overlooked, but the stories unfold if we care to see them. From a formal perspective, we could say her camera missed the perfect framing, but had there been a conscious hairbreadth of a gap between her seeing and shooting, the image would never have turned out this way.
In her afterword, the artist remarks on transcending bounds, and what is travel if not going beyond limits and demarcations? The divisions may not be just between towns and countries, but between this world and the next. To travel is to see the world through the gaze of the world beyond, and photographs give us clues to navigate our uncertain present.
My eyes chance to fall upon the image of a young mother carrying an infant swaddled in the folds of a hanten padded kimono. What year might this have been? And not just one such image; the artist captured many such mothers. Come to think of it, this entire collection looks almost exclusively at women and children. Boys or girls, who can tell? As the saying goes, until the age of seven, children are little gods. The anonymous women remain without exception quiet and expressionless, or else are seen from behind or in shadow. Look closely, and the spirit of the artist herself floats into view. If we follow these photographs, another Nishimura Tamiko is cast in high relief: the living image of an artist who, in the course of her travels, gazed unflinchingly on fellow women.
Hirashima Akihiko is a photographer and editor
Translation: Alfred Birnbaum
English editing: Mark Robinson
■平嶋彰彦 ひらしまあきひこ
写真家、編集者
1946年千葉県生まれ。1969年毎日新聞社に入社。『毎日グラフ』『サンデー毎日』の写真取材に携わる。のち編集に転じ『宮本常一 写真日記集成』『グレートジャーニー全記録』などを手がける。2009年退社。共著に『昭和二十年東京地図』など。
◆ときの忘れものは2014年2月5日[水]―2月22日[土]「西村多美子写真展―憧景」を開催しています。
出品リストはホームページに掲載しました。

本展は六本木の ZEN FOTO GALLERY との共同開催です(会期が異なりますので、ご注意ください)。
第1会場 ZEN FOTO GALLERY
「西村多美子写真展―しきしま」
会期:2014年2月5日[水]―3月1日[土]
※日・月・祝日休廊
第2会場 ときの忘れもの
「西村多美子写真展―憧景」
会期:2014年2月5日[水]―2月22日[土]
※会期中無休
●『西村多美子写真展―憧景』の出品作品を順次ご紹介します。
出品番号5:

西村多美子 Tamiko NISHIMURA
《福井県》
(p.97)
1970年代初期
ヴィンテージゼラチンシルバープリント
イメージサイズ:36.5×54.8cm
シートサイズ :44.6×54.8cm
サインあり
------------------------
出品番号6:

西村多美子 Tamiko NISHIMURA
《笠間付近、茨木県》
(p.101)
1970年代後期
ヴィンテージゼラチンシルバープリント
イメージサイズ:36.5×54.7cmm
シートサイズ :44.6×54.7cm
サインあり
こちらの作品の見積り請求、在庫確認はこちらから
●西村多美子写真集『憧景』のご案内
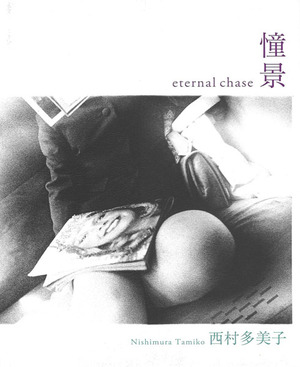 2012年10月31日
2012年10月31日
グラフィカ 発行
27.7x22.8cm(A4変型判)
ハードカバー 142ページ
写真点数:88点
限定500部
価格:4,500円(+税)
※送料別途250円
西村多美子の若き日(1970~83年)の旅の記録。1970年代初頭に北海道、東北で撮影されたものを中心に、東京、関東近郊、北陸、関西で撮られたもの、またその後80年代初頭にかけて撮影されたものも含む「西村多美子の血の轍ともいうべき若き日の旅の記録」です。
未だ都市に塗られていない、それぞれの土地の独自性が西村多美子の眼だけではなく身体全体にによって捉えられた渾身の写真です。
平嶋彰彦
(西村多美子写真集『憧景』より再録)
本書は西村多美子の血の轍ともいうべき若き日の旅の記録である。
写真の日付は1970年から83年ごろというから、作者が20代から30代だったときにうつしたものである。撮影地は北海道・東北が大半をしめているが、関東・北陸・関西と広範囲にもおよんでいて、なかには地元の東京でうつしたものもふくまれている。
1970年といえば、連合赤軍による日航機よど号のハイジャック、日米安全保障条約をめぐる全国的な反対行動、大阪で開催された万国博覧会、あるいは三島由紀夫の市ヶ谷自衛隊駐屯地における割腹自殺などの事件がおもいだされるが、旧国鉄のキャンペーン「ディスカバー・ジャパン」がはじまったのもこの年である。
このキャンペーンは個人旅行者や女性旅行客の拡大をはかったもので、新聞・雑誌メディアをつうじて喧伝されたばかりでなく、旧国鉄がスポンサーになり「遠くへ行きたい」の題名でTV番組まで製作された。山口百恵の「いい日旅立ち」(谷村新司作詞・作曲)は1978年のヒット曲だが、もともとは「ディスカバー・ジャパン」のテーマ曲としてつくられている。
北海道の倶知安駅で列車の窓からうつした夏の羊蹄山の写真がある(30-31ページ)。
 「倶知安、北海道」
「倶知安、北海道」プラットホームのむかいに停車しているのは9615型の蒸気機関車である。機関車に作者の興味はなかったかもしれないが、運転手は好奇の目でカメラを見つめている。ふりかえってみれば、このころまではまだ女の一人旅はめずらしかったのである。
「あるくみるきく」は民俗学者の宮本常一*が主宰した月刊の旅雑誌としてしられる。スポンサーは近畿日本ツーリストで、創刊されたのは1967年である。雑誌名の「あるくみるきく」は宮本の旅の思想を要約したもので、「旅にまなぶ」(「宮本常一著作集31」所載)にはつぎのような趣旨の文章がつづられている。
<旅をするのはなにかを発見するためである。それには歩いてものを見てみるしか方法はない。ものを見ていくと、わからないことが増えてくるが、わからないことを確かめて、明らかにするところに、旅の目的がある。>
宮本常一を引き合いにだしたのは、わからないことを確かめて、明らかにするという宮本の旅の思想と作者の写真の面構えにどこか通いあうものを感じるからである。もとより作者の写真紀行は「ディスカバー・ジャパン」の観光旅行でもなければ、民俗採訪の学術調査ともちがっている。どちらかといえば前代までの物見遊山や霊地巡礼といった庶民信仰の旅によほどちかく、そういってよければ芭蕉*の俳諧紀行をほうふつさせるものである。
芭蕉の紀行文集「野ざらし紀行」は旅を死出の道行にたとえたものである。死出の道行とはいっても、実際はあの世への片道切符でないわけだから、旅立ちのときの「野ざらしを心に風のしむ身かな」のおもいつめた心境は、旅の途中で「死にもせぬ旅寝の果よ秋の暮」と諧謔的によみなおされている。野ざらしとは野にさらされて白骨化したサレコウベのことである。芭蕉は野ざらしとなることを旅の理想にしているわけだが、そこには風狂の戯れ言としてかたづけられない、古代からの民俗的な死生観がうもれている。
8世紀に編纂された「古事記」と「日本書紀」に旅の記述がでてくる。イザナギが死んだ妻のイザナミを黄泉国にたずねる神話でも、アマテラスの神田を汚すなどの罪をおかしたスサノヲが根の国に追放される神話でも、旅するものは神であり、その行き先はあの世である。いずれも死の世界をめぐることにより、神が誕生するとか復活するとかいう物語構造になっていることは見のがせない。
「日本書紀」の一書によれば、スサノヲは青草を結いたばねた笠蓑をまとっていたが、これを目にした八百万の神々は誰ひとりとして宿をかさなかった。笠蓑は雨つゆにぬれるのをふせぐ道具というよりも、死者が身につける死装束の象徴であった。筆者の郷里は房総半島の南部であるが、このあたりでは死者の命日をタチビ(立ち日)、遺骸を埋葬する場所をタチバ(立ち場)または訛ってタチューバとむかしから呼んできた。タツ(立つ)とはあの世への旅立つことをさしてそういうのである。
芭蕉は「奥の細道」の序章で、どうして旅をするのかを自問自答したあげく、「片雲の風にさそわれて、漂泊の思ひやまず」とも「そヾろ神の物につきて心をくるはせ、道祖神のまねきにあひて取るもの手につかず」ともかいている。旅に出ようとする発心は主体的な意識であるにもかかわらず、自分では手におえないなにものかであり、始末のわるいやっかいなしろものだというのである。その観点からすれば、旅の世界は生死や性愛の問題とよくにている。
上記の文中にある「そヾろ神」は芭蕉の造語だとおもわれるが、東北地方の旧家にはオシンメイサマともオシラサマ・オクナイサマともよばれる正体不明の神をまつる風習があったことを、柳田國男*が「大白神考」(「定本柳田國男12」所載)にかきとめている。
「オシンメイサマを持ち伝えた旧家の主婦は、夢にしばしば神の催促を聴き、一年に一度はこの木像を背に負うて、立ち出でゝあるきまわらぬとぶらぶら病にかゝる」
主婦たちをそそのかしたというその木像をカメラに置きかえてみればわかりやすい。西村多美子という写真家は、正体不明の神に心を狂わせて漂泊の旅にでたといわれるこの忘れられた女たちの後裔であるようにおもわれてならない。
うつす(写す)という語を白川静*の「字訓」でひいてみると、本来のものを他に移して、その色や形を再現することである、とかいてある。写すは他動詞である。写すは模すにつうじる。
写すことは見るという知覚行動をふまえている。見るという言葉は目と同根で、目にとめて見る、その機能をいう、とも白川静はかいている。日本語の見るは、たんにものを眺めることをさししめすだけでないということだ。ものを観察する・知る・判断する・世話をするなど多義的な意味をふくんでいるのである。古くは男女が契ることまでも見るといったらしい。男と女がものを隔てずにあうことは夫婦関係にはいることに解されたともいわれている(「新潮国語辞典」)。
本書にはカメラをじっくり構えてとったとおもわれるような写真はまずみあたらない。出会いがしらにそっけなくうつしとったものばかりである。対象が人物であっても事物であってもそれは変わらない。安定した構図、正確な露出や測距は二の次になっている。目にとまるとか気にかかるものがあれば、なんであってもかまわない、ぐずぐずしないで、とっさにうつしとろうとする姿勢がはっきりとうかがえる。
西村多美子の写真につらぬかれている方法論には、うつすという作者の主体的なはたらきかけよりも、目標物はおのずからうつってくるものであるという一種共犯的な期待と他力本願的な確信があるようにおもわれる。ものを見るとか見られたりするのは相手があってのことで、見るという知覚行動は相手から触発されることがなければ成立しない。見ることと見られることは相互規定的なきわどい関係にある。誤解をおそれずにいえば、西村の写真はものをうつすというよりも、ものが憑くという印象を強くうける。憑くというのは、ものがのり移って憑りつくことをいうのである。
場当たり的とも刹那的ともいえる撮影方法とは対照的に、プリント作業には神経質なくらいたっぷりと時間と手間をかけている。砂をまぶしたような銀粒子のあれた画面をみれば、高温か長時間かはともかく、常識はずれなフィルム現像をしているのは想像にかたくない。しかし手間ひまのかかるのはそのせいばかりではないだろう。コントラストを強調した奥行のふかい白黒の色調や手のこんだ焼き込みと覆い焼きは、日本語の見るという言葉における観察する・知る・判断するという知覚行動の試行錯誤を示唆している。
巻末に掲載された撮影地の一覧をみると、どこもいわくや因縁があって馴染みのある地名ばかりがならんでいる。あいつぐ炭鉱の閉山でゆれる北海道の夕張*や、かつて米軍試射場反対闘争*のあった石川県の内灘など、戦後史にのこる著名な社会的事件や住民闘争のあった町にも足をはこんでいる。旅にさいして芭蕉の俳諧紀行における枕詞に類する目あてのようなものが作者にもあったはずであるが、地名を喚起させる象徴性をもつ事物や事象をうつしこんだ写真はわずかしかみあたらない。あたりまえのようにどこにもありふれている場面ばかりなのだが、どういうわけか写真を見はじめると目が離せなくなる。
一例をあげれば、北海道の旭川でバラック風の建物が軒をつらねる場末の繁華街をとった写真がある(18-19ページ)。

「旭川、北海道」
大通りには雪が凍てついたまま残っている。歩道に目をやると、こちらにむかって歩いてくる手さげ袋をもち足元はゴム長靴の女。すぐ後ろに、耳あて帽子をかぶった母親と幼児の二人連れ。いちばん手前の家では玄関のガラス戸を半開きにし、やはり親子とおもわれる女と少年が通りをながめている。少年はトックリのセーターにカーディガン姿。軒先には自転車がならべられ、古風な木製の脚立がたてかけてある。
よくみると、少年はあおぐように視線をカメラにそそいでいる。カメラの位置はそれよりも高い。どうやら作者はバスの車窓からうつしているらしい。通りすがりの旅行者に通りすがりの人たちが目にとまり、交差点をバスが曲がるつかの間に名前のないいくつもの人生がすれちがう場面である。ありふれた偶然が目をみはらせる情景になっている。地味な画面構成でうっかり見過ごしかねない写真だが、絵解きをすればそんなことになる。ものを見てからカメラを構えるのではまにあわない。見ることとうつすことが切れ目のない連続行為として意識されていなかったら、こんなふうにものはうつってこない。
作者はバスばかりでなく移動中の列車のなかや船のうえからも写真をとっている。なかにはホテルの部屋からとったとみられるものもある。大半は歩いてとった写真であるが、立ち止まらずに歩きながらカメラをむけているようにおもわれる。それは眼差しをそそぐのがつかの間の瞬間であるという作者の心構えをしめしている。男女の関係にかぎらない。見ず知らずの相手を理由もなくじろじろと見ていたらただですまなくなるのは、今も昔もかわりはしない。自由にものを見ることが許されるのは、つかの間という制限された時間でしかないのだ。見ないということが人間社会の安全装置になっていることに私たちはもっと注目していいのではないだろうか。
この写真集の題名を作者は「憧景」と名づけている。前作の「実存」(2011年、グラフィカ編集室)は唐十郎*の状況劇場を1968-69年に取材したものである。芝居小屋が近代以前に悪所とよばれたのは、そこが無縁・公界の非日常的な世界とみなされたからである。旅とは家をはなれることで、日常的な時空間からの離脱もしくは追放を意味する。旅も芝居も無縁・公界の非日常的な世界に帰属する。芝居役者が発生史的に道々の者であったことをかんがえれば、仮そめとはいえ座付き写真家を体験した作者が旅に転位をもとめたことは驚くにあたらない。「憧景」とは具象化された「実存」をさしている。
本書のあとがきで、作者は結界をこえることに言及している。旅をするとは越境することで、結界をこえることにほかならない。村境や国境は同時にこの世とあの世を分かつ場所でもあった。だから注連縄をはるとか、塞の神や道祖神をまつったりしたのである。さきにのべたスサノヲの神話にみられるように、わが国の古い民俗では、旅をするものは死者か神仏のいずれかに見立てられた。芭蕉は野ざらしのサレコウベとなることを旅の理想としている。物見遊山や霊地巡礼は、いったん死んだことにし、あの世をめぐりあるき、ふたたびこの世によみがえる、という擬死再生の庶民信仰であった。芭蕉の「死にもせぬ旅寝の果よ秋の暮」の句は、風狂の俳諧紀行もまたそうした歴史的習俗をふまえたものであったことをものがたっている。
旅をするのは、死者の眼差しをもってあの世からこの世を見るためである。死者の関心は、わが身の不在によって生き残った人たちが苦労を強いられないかどうかにある。作者は目にとまり胸騒ぎを感じれば、何であろうとかまわずうつしている。胸騒ぎをおぼえるのはなにか現実的な理由があるからである。写真は来しかた行くすえの定まらないわが身と現実世界の在り方をさぐりだす糸口でもある。写真にうつされたものは夢の断片とおなじで脈略がないようにみえるが、作者が見ようとしてうつした現実であることは否定のしようがない。西郷信綱*によれば、夢が現実と対比されるのは後世になってからのはなしで、古代までさかのぼれば、夢は現実に見るもので、現実を写すものであったということである(「古代人と夢」)。
ふと、若い母親が赤ん坊を背負った写真に目がとまる。赤ん坊をねんねこ半纏で背中にくるまなくなったのはいつごろからだろうか。1人だけではない。作者はおなじような母親をくりかえしうつしている。そういえば、この写真集では女と子どもばかりに目がむけられていることに気づく。7歳までは神のうちで、子どもは男も女もないが、おとなの男となるとは数えるほどしか登場しないのだ。それも女と2人連れで、男だけが大きくうつっているのは1枚もない。その女といえばだれもかれも黙々として名前のない表情をしている。そうでなければ後姿であるか、影にかくれて表情がみえない。それをくいいるように見つめている作者の姿がおのずと目に浮かんでくる。
作者の西村多美子は1948年生まれで、72年に結婚し74年に出産を体験しているという。それぐらいのことしか知らないのだが、知らなくともいっこうにかまわない。写真をたどっていけば、旅のなかで目にとまった女たちの生きる姿とはまぎれもなくもう1人の西村多美子であったことが浮き彫りになってくる。
(ひらしまあきひこ)
*脚註
宮本常一 みやもとつねいち(1907-1981)
民俗学者 山口県周防大島生まれ
戦前より日本全国をめぐり歩き、膨大な民俗の記録を残した。
著書『忘れられた日本人』、『庶民の発見』、『私の日本地図』 全15巻。
没後に出版された書籍『宮本常一写真・日記集成』(上下巻+別巻)2005
松尾芭蕉 まつおばしょう(1644-1694)
江戸前期の俳諧師 伊賀国(現三重県)生まれ
『野ざらし紀行』は、1684年に江戸から故郷の伊賀上野への旅を中心に、句と文をあわせて記した紀行文。『おくのほそ道』は1689年に江戸を出て、東北、北陸を巡り大垣までの旅をやはり俳句と文を合わせて綴った紀行文。
柳田國男 やなぎだくにお(1875-1962)
民俗学者 兵庫県生まれ
日本民俗学の黎明期を担ったもっとも著名な一人。東大で農政学を学び、農務官僚となる。全国への視察や新渡戸稲造との交流などを契機に、各地の民間の習俗、信仰への関心を大きくする。1913年雑誌『郷土研究』刊行。
著書『遠野物語』、『蝸牛考』、『海上の道』
白川静 しらかわしずか(1910-2006)
中国文学者 福井県福井市生まれ
古代中国文学、漢字の研究者。漢字の発生と変化を、人と世界との交流による啓示と応答の表象として読み解く、深遠な漢字世界の研究を遺した。
著書『字統』、『字訓』、『字通』(辞書)『漢字の世界1、2』『漢字』、『中国古代の民俗』
北海道夕張市
明治初期にドイツ人技師ライマンが石炭鉱脈の可能性を指摘したことで調査が始まり、明治中期から次々に炭鉱がひらかれた。北海道炭礦汽船(通称・北炭)が夕張地域で最大の事業主。他に三菱鉱業による大夕張炭鉱など。戦後、1960年頃の最盛期のあと、エネルギー政策の石油への転換、大規模な事故などにより、1970年代前半より閉山が進む。
80年代に観光による振興を目指し、ジェットコースターや観覧車まで作られ、モデル自治体として当時の政府から表彰されるが、破綻。2007年に財政再建団体となる。
米軍試射場反対闘争(内灘闘争)1952-57
石川県河北郡内灘村の海岸砂丘を朝鮮戦争で使用する砲弾の試射場として米軍が接収したことに反対した村民の抵抗活動に、学生をはじめ全国から労働組合団体などが加わり、戦後の米軍基地反対闘争の口火となった。
唐十郎 からじゅうろう(1940- )
劇作家、俳優 東京都生まれ
明治大学文学部演劇学科卒業後、「シチュエーションの会」を立ち上げ、後に「状況劇場」と改名する。60年代末期からのアンダーグラウンドの時代に、寺山修司の「天井桟敷」などと共に中心的存在だった。新宿の花園神社をはじめ、様々な場所に紅テントを設営し公演を行った。俳優陣は、初期は、麿赤児、四谷シモン、李礼仙、藤原マキ、大久保鷹、不破万作など。その後も根津甚八、小林薫、佐野史郎、金守珍などの個性の強い役者が揃っていた。
代表作『腰巻きお仙・義理人情いろはにほへと篇』『ジョン・シルバー』、『少女仮面』(早稲田小劇場)。戯曲以外の著書 『特権的肉体論』 、『佐川君からの手紙』、『海星・河童-少年小説』
西郷信綱 さいごうのぶつな(1916-2008)
国文学者 大分県生まれ
戦後における古代文学研究の第一人者。歴史学、民俗学など他の学問分野の観点を積極的に取り入れ、国文学研究に新しい地平を切り開いた。著書 『貴族文学としての万葉集』 、『古事記の世界』、『古代人と夢』 、『古事記注釈』『梁塵秘抄』 、『斎藤茂吉』
*脚註文責:グラフィカ編集室
-----------------------------
Reflect Forward: the Journey is the Route
Akihiko HIRASHIMA
This book, we might say, traces the pulse of Nishimura Tamiko's youth on the road. The images were shot between her 20s and 30s – from around 1970 to 1983. Most were taken on the northern island of Hokkaido and through the northeastern Tohoku area, but also across the Kanto (including her hometown Tokyo), Hokuriku and Kansai regions.
Nineteen-seventy was an eventful year for Japan. There was the Red Army hijacking of a JAL passenger plane, massive nationwide protests against the US-Japan "AMPO" security treaty, Osaka Expo '70, and Mishima Yukio's seppuku suicide at the Japan Self-Defense Force Barracks in Ichigaya. The same year saw the launch of the now-privatised Japan National Railway's "Discover Japan" campaign, targeting prospective solo and women travellers. JNR even sponsored a regular TV programme, Touku e Ikitai ("I Want to Travel Far").
In the photograph of Mt. Yotei (pp.30–31), taken from a train window at Kutchan Station in Hokkaido, we see a steam locomotive across the tracks. The train may not have interested Nishimura at the time, though her camera is attracting attention, as the driver is peering at it curiously. Solitary women travellers were obviously still a rarity then.
The title of folklorist Miyamoto Tsuneichi's monthly magazine Aruku Miru Kiku ("Roam, See, Hear"), sponsored by the Kinki Nihon Tourist agency and first published in 1967, sums up his travel philosophy. In the article Tabi ni Manabu ("Learn by Travelling"), he says: "We travel in order to discover things. There really is no other way than to go see for yourself. The number of unknowns may increase when we go see things. Another reason to travel is to verify and clarify the unknown."
Whatever similarities we may sense between Miyamoto's thinking and Nishimura's photographic forays, her travels were neither Discover Japan tours nor folklore surveys. If anything, they were closer to folk pilgrimages of a bygone era, to places haloed and spiritual. The sort of personal quest that sent the poet Basho on his haiku wanderings.
In Nozarashi Kiko ("Bare Bones Travelogue"), Basho likens travel to the "way to death." Basho's ideal of faring on and on, until reduced to bones, cannot be dismissed as the mere musings of an eccentric. It underscores a Japanese view of life and death that has been popular since ancient times.
Travel also figures in the 7th century Kojiki ("Record of Ancient Matters") and 8th century Nihon Shoki ("Chronicles of Japan") imperial codices. For example, the descent by ancient deity Izanagi into the Underworld (Yomi) in search of his deceased wife Izanami. Nihon Shoki shows the sun goddess Amaterasu banishing her brother, the storm god Susano-o, to the Root World (Ne no Kuni), for defiling the sacred rice fields. Both are mythic journeys leading to divine rebirth.
In his preface to Oku no Hosomichi ("Narrow Path to the Far North") Basho asks himself why he travels: "A lone cloud blown about in the wind cannot but imagine itself adrift," he writes. "Driven to distraction by things divine, the ancestral guardians of the road beckon toward what lies ever out of reach." While the impetus to set forth may be a conscious subjective choice, the prospect literally gets out of hand and ends up being a curse. In that sense, traveling is as unpredictably fraught as life and death – or love and sex.
The pioneering folklore scholar, Yanagida Kunio, notes in his article Oshiragami Ko that old households in Tohoku customarily practised observances related to a mysterious spirit known as Oshinmei-sama, Oshira-sama or Okunai-sama. "Matrons of these families who subscribe to the Oshinmei-sama cult frequently hear divine promptings in dreams," he writes, "and will incur serious illnesses should they not to go walkabout, shouldering his wooden statue, once a year." Exchange the onerous wooden image for a camera, and it is not difficult to see our photographer Nishimura as a latter-day scion of those forgotten women, who set off wandering possessed by a mysterious spirit.
The Japanese transitive verb utsusu, which can mean "to photograph", originally meant "to move things from one place to another." It since came to include such notions as reproducing colour and form, hence copying or emulating. It implies the perceptual act of seeing. Likewise, the verb miru (見る) "to see" stems from the Chinese character me (目), "eye" – that is, the function of fixing one's eyes upon something. Thus, "to see" in Japanese refers not only to gazing, but covers a broad range of meanings from observing, knowing, judging, and even caring. In olden times, it seems that male-female relations were also a kind of "seeing."
None of the photos in this book are very studiously composed, whether the subjects are people or things. Steady composition, correct exposure and focal range are secondary. Rather, what clearly comes across is Nishimura's straightforward stance toward shooting whatever caught her eye, without hesitation or undue posturing.
Her photographic method is less that of an artist subjectively seeking to capture an image than of letting the target object show itself. She joins in a kind of conspiratorial expectation, or belief in salvation by "other powers". Thus seeing and being seen are mutual, the perceptual act of seeing must be inspired by the other; the relationship of the seer to the seen prescribes a tenuous reciprocity.
Counter to the happenstance ephemerality of photo-graphing, however, the act of printing requires assiduous, time-consuming effort. To look at the silver-particle sandstorms of Nishimura's grainy images, we can easily imagine she developed her films using high temperatures or long bath times, or other unorthodox methods. The deep blacks and high-contrast whites, the laborious hand-shading techniques, attest to considerable trial and error.
Nishimura must have had her benchmarks, not unlike the makura-kotoba set-phrases of Basho's haiku travelogues. But very few of the events and things shown in her photos speak of specific locales. Most are of commonplace scenes and yet their evocative power captivates us.
The image of the shack-like facades of a rundown street in Asahikawa, Hokkaido (pp.18-19), for instance, shows the icy remnants of snow in the gutter by a footpath where walks a woman in gumboots with a carrier bag. Right behind her is a mother in an ear-muffed hat with her child. The glass door to the closest house is half-open, revealing what seems to be a mother with her son in a turtleneck and cardigan, looking out on the street. A row of bicycles lines the street and an old wooden ladder leans up against some eaves. Look carefully and you notice the camera is peering directly at the boy from a slightly elevated position. Perhaps Nishimura took this from a bus window. These unnamed people going about their everyday lives must have caught her eye just as the bus turned at an intersection. A chance glimpse that makes us see the poetry in the everyday. The composition is so understated as to be easily overlooked, but the stories unfold if we care to see them. From a formal perspective, we could say her camera missed the perfect framing, but had there been a conscious hairbreadth of a gap between her seeing and shooting, the image would never have turned out this way.
In her afterword, the artist remarks on transcending bounds, and what is travel if not going beyond limits and demarcations? The divisions may not be just between towns and countries, but between this world and the next. To travel is to see the world through the gaze of the world beyond, and photographs give us clues to navigate our uncertain present.
My eyes chance to fall upon the image of a young mother carrying an infant swaddled in the folds of a hanten padded kimono. What year might this have been? And not just one such image; the artist captured many such mothers. Come to think of it, this entire collection looks almost exclusively at women and children. Boys or girls, who can tell? As the saying goes, until the age of seven, children are little gods. The anonymous women remain without exception quiet and expressionless, or else are seen from behind or in shadow. Look closely, and the spirit of the artist herself floats into view. If we follow these photographs, another Nishimura Tamiko is cast in high relief: the living image of an artist who, in the course of her travels, gazed unflinchingly on fellow women.
Hirashima Akihiko is a photographer and editor
Translation: Alfred Birnbaum
English editing: Mark Robinson
■平嶋彰彦 ひらしまあきひこ
写真家、編集者
1946年千葉県生まれ。1969年毎日新聞社に入社。『毎日グラフ』『サンデー毎日』の写真取材に携わる。のち編集に転じ『宮本常一 写真日記集成』『グレートジャーニー全記録』などを手がける。2009年退社。共著に『昭和二十年東京地図』など。
◆ときの忘れものは2014年2月5日[水]―2月22日[土]「西村多美子写真展―憧景」を開催しています。
出品リストはホームページに掲載しました。

本展は六本木の ZEN FOTO GALLERY との共同開催です(会期が異なりますので、ご注意ください)。
第1会場 ZEN FOTO GALLERY
「西村多美子写真展―しきしま」
会期:2014年2月5日[水]―3月1日[土]
※日・月・祝日休廊
第2会場 ときの忘れもの
「西村多美子写真展―憧景」
会期:2014年2月5日[水]―2月22日[土]
※会期中無休
●『西村多美子写真展―憧景』の出品作品を順次ご紹介します。
出品番号5:

西村多美子 Tamiko NISHIMURA
《福井県》
(p.97)
1970年代初期
ヴィンテージゼラチンシルバープリント
イメージサイズ:36.5×54.8cm
シートサイズ :44.6×54.8cm
サインあり
------------------------
出品番号6:

西村多美子 Tamiko NISHIMURA
《笠間付近、茨木県》
(p.101)
1970年代後期
ヴィンテージゼラチンシルバープリント
イメージサイズ:36.5×54.7cmm
シートサイズ :44.6×54.7cm
サインあり
こちらの作品の見積り請求、在庫確認はこちらから
●西村多美子写真集『憧景』のご案内
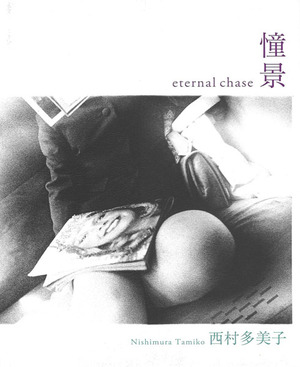 2012年10月31日
2012年10月31日グラフィカ 発行
27.7x22.8cm(A4変型判)
ハードカバー 142ページ
写真点数:88点
限定500部
価格:4,500円(+税)
※送料別途250円
西村多美子の若き日(1970~83年)の旅の記録。1970年代初頭に北海道、東北で撮影されたものを中心に、東京、関東近郊、北陸、関西で撮られたもの、またその後80年代初頭にかけて撮影されたものも含む「西村多美子の血の轍ともいうべき若き日の旅の記録」です。
未だ都市に塗られていない、それぞれの土地の独自性が西村多美子の眼だけではなく身体全体にによって捉えられた渾身の写真です。
コメント