連載「瑛九 - フォト・デッサンの射程」
第5回「Just silence ... Just nothing ...-第33回瑛九展・湯浅コレクション(その1)」
Just silence ... Just nothing ...ニュー・オーダーのセカンド・アルバム『Power, Corruption & Lies』(1983)のB面の最初を飾る「Your Silent Face」の印象的なフレーズが私の耳に届けられ、ふと、私を瑛九に導いてくれた方を思い出す。瑛九の多面的な活動を、レコード盤のA面とB面の関係に喩えてみせた人だから。A面が終わり、レコード盤を裏返し、B面をセットする。チリチリとした静寂の裂け目から射し込む光のように、この曲が静かに流れ始めると、時折、瑛九の《田園》を思い出す。虚空に放たれる「Just silence ...」、「Just nothing ...」、過ぎた日々を彷徨うかのような、Your Silent Face。
2023年11月12日、シンポジウム「瑛九再考」
いま、この原稿を書いているのは、2023年11月16日。ただ、例によってニュー・オーダーの楽曲の助けを借りた上述のイントロは、10月22日に書いている。その時、ほどなく、私を瑛九に導いてくれた方、すなわち、埼玉県立近代美術館での私の先輩学芸員である大久保静雄さんにお目にかかる機会が訪れるとは、予想できていなかった。
事の次第は、次のとおりである。「さいたま国際芸術祭2023」の関連プログラムとして「創発inさいたま」が立案した「瑛九再考」というシンポジウムの準備中、浦和にある「瑛九のアトリエ」が取り壊される危機に瀕していることが判明したという。去る11月12日、浦和において開催されたシンポジウム「瑛九再考」において、この件に関する経緯と現状が報告され、多くの登壇者が、それぞれの立場からの報告、提言、発信を行った。大久保さんとは、このシンポジウムの会場近くで遭遇したのだった。
この連載の第2回から第4回において、ようやく記録を公開することができた2013年のギャラリー・トークでは、瑛九の活動の諸相を、マトリクスを用いて解析することを試みた。その際、まず、「マトリクスA=絵画のマトリクス」と「マトリクスB=写真のマトリクス」という設定を考えた。そのアイデアは、2011年の「生誕100年記念 瑛九展」の企画段階において、大久保さんが、瑛九の活動をレコード盤のA面とB面の関係になぞらえてとらえるという、極めて示唆に富む提案をされたことに刺激されたものである。だから、10年前のギャラリー・トークの記録公開に取り組んでいる私にとって、そのギャラリー・トークの原点となるアイデアに示唆を与えてくださった大久保さんと、このタイミングでお会いできることに、深い感慨を覚えたのである。
そのシンポジウムのことは、いずれ主催者側がしかるべき記録をとりまとめて公開してくれるのではないかと思われるため、ここでは言及しない。ただ、この日、シンポジウムの最後に発言を求められた際、時間的な制約から、断片的な発言となってしまったため、シンポジウムの参加者やこの連載の読者と共有したい事柄を、ここに記しておきたい。
まず、「瑛九のアトリエ」という呼び方に、少し戸惑いを感じる。瑛九が制作をした場所であるから、アトリエという呼び方をするのは間違いではない。しかし、あの家は、まず、何よりも、瑛九と瑛九夫人の都さんの、二人の生活の場であったはずだ。そして、瑛九は、都さんとの生活の場において、制作を続けていた。だから、あの家は、「瑛九と都さんの家」と呼んだ方がいい。さらに、瑛九は都さんのことを「ミーニョ」と、都さんは瑛九のことを「ヒーチョ」と、エスペラントの愛称で呼んでいたという(「ヒーチョ」は瑛九の本名・杉田秀夫に由来するのだろう)。そのことをふまえて、あの家を、私は「ヒーチョとミーニョの家」と呼びたいと思う。そこまでは、当日、話すことができた。
だが、ここで、もうひとつ進めて、二人の名前の順番を入れ替え、この家を「ミーニョとヒーチョの家」と呼んでみたい気がしてきた。「ミーニョ」こと都さんが先にくるのは、生活という面においては、都さんが切り盛りをしていた訳であり、その生活の基盤があってこそ、瑛九は制作に集中することができたはずだからである。何より、瑛九がこの家で生活し制作に打ち込んだ期間は10年に満たないが、都さんは瑛九の没後、50年以上、この家での生活を続けたのだ。
瑛九の生活と制作を支え、瑛九没後も長きに渡ってこの家と瑛九の作品を守り続けた都さんへの敬意を表し、この家を「ミーニョとヒーチョの家」と呼びたいと思う。シンポジウムの当日は、初めてこの家を訪れた日に都さんから伺った話を手短に報告することしかできなかった。そのため、以下では、シンポジウムの参加者やこの連載の読者と共有したい事柄を、記しておきたい。
1997年4月24日、「ミーニョとヒーチョの家」、都さん
私が「ミーニョとヒーチョの家」を初めて訪れたのは、1997年4月24日のことである。この年の6月から、埼玉県立近代美術館において、企画展「光の化石-瑛九とフォトグラムの世界」が開催されることになっていた。私はその展覧会を担当しており、大久保さんから、都さんに挨拶に行くようにと言われていたのである。当日は、当時の学芸部長の水野隆さん、大久保さん、筑波大学の五十殿利治さん、それに私という、4名での訪問となった。五十殿さんは、刊行準備が進められていた『瑛九作品集』(日本経済新聞社)に収録される論文を執筆されていらして、都さんにご挨拶をしたいと、大久保さんに連絡を入れていらしたとのことであった。
都さんに負担をかけないために、一緒に訪問するという段取りになったのであるが、当日、極度の緊張が私を襲ったことは言うまでもない。それは、私と同じく、この日、初めて都さんにお目にかかることになる五十殿さんも同様であったようである。都さんにご挨拶をすませ、五十殿さんは『瑛九作品集』のことをお話されて、私は「光の化石」のことを説明し、その後は、都さんのお話を伺う貴重な時間を過ごした。その途中、五十殿さんは、腰が痛いので腰を伸ばしてきますと、一度、席を外され、庭に出られて、腰を伸ばしていらした。それだけ緊張されていらしたのだ。
その時、ああ、五十殿さんでもあれだけ緊張するのだから、自分が極度の緊張に襲われるのも無理はないなと思ったのである。もちろん、私も、緊張を少しでもほぐすべく、そのタイミングを逃さず、五十殿さんに続いて庭に出て、凝り固まった体をほぐそうとした。そして、ああ、点描の絵を庭に出してその絵に囲まれたいと瑛九が語った、その庭に、いま、自分が立っているのだと、緊張の只中にありながら、深い感慨に浸ったことも、その日の忘れ難い思い出である。
いま、手元に、「光の化石」の時のノートがある。このノートには、1997年4月24日に都さんから伺った話の要点がメモしてある。極度の緊張の中でも、頭の中でテープレコーダーに録音するように、都さんのお話を、一言残らず記憶しておこうと必死だった。だから、同行した方々と別れて一人になってすぐ、頭の中のテープレコーダーを再生するようにして、都さんの口調や身振り手振りを思い出しながら、急いでメモを記したのである。
普段、ノートのメモを読み返そうとすると、自分でも読めないほどひどい字なのであるが、この時の都さんのお話を記したメモは、どういうわけか、比較的まともで、十分に読むことができる。「ミーニョとヒーチョの家」で都さんと対面している時の緊張感が持続していて、その緊張の中で、メモを書いたのだろうか。あるいは、いつか、都さんが話してくださったことを思い出せなくなってしまった時に、このメモが読めなくならないように、きちんと読める字で書かなければ、それだけ大事な記録なのだと、自分に言い聞かせたのだろうか。何も思い出せないが、メモがあってよかった、ただ、そう思う。
都さんが話してくださったこと
以下、都さんがお話してくださったことを、書いておきたい。なお、シンポジウム当日は、時間の制約から、以下の都さんのお話の7~8割を読み上げるにとどめた。
・瑛九は命を縮めて制作に打ち込んでいた。
・浦和から外へ出たことは極めて少ない。
・展覧会のオープニングのために背広を着てほしいと言われたが、持っていなかった。
都さんが妹夫婦に相談して調達したが、一回しか着なかった。
・絵の具がついたままの服で外出し、そのまますぐ帰る。着替えると制作中のイメージがとんでしまうから。
・銅版や印画紙を買いに神田へ行くのも都さんだった。
・瀧口修造によるタケミヤ画廊の展覧会の時も、画廊につめるのは都さんで、瑛九は制作していた。
・人づきあいは苦手で、芸術論以外は会話しなかった。
・走ると手足が一緒になったのを駅のホームで見た。
・運動神経は良くなかった。
・自転車に乗れず、移動すると、一緒に倒れた。
・橋を渡ると「飛び込め」という強迫観念があって、ひとりで橋を渡れなかった。車か、付き添いが必要。
・傘をさしても肩にかけてしまい、雨にぬれていた。
・浦和の家は都さんがみつけた。かやぶきの家だった。
・当時2軒しかなく、田んぼ、林だった。
・富本憲吉の知り合いの石井さんという陶芸の人の家だったらしい。
・犬、猫を飼った(宮崎での話)。
・浦和でも犬を飼った、にわとりも。
・黄色は瑛九において重要な色である。
この日のシンポジウムは、感慨深いものとなった。それは、会場の入口で、私を瑛九に導いてくださった大久保さんとお会いし、一緒に会場に入り、隣の席でシンポジウムを聞くことになったからである。登壇者には、埼玉県立近代美術館での私の後輩学芸員である吉岡知子さんと、2011年の「生誕100年記念 瑛九展」の時に苦楽をともにしたうらわ美術館学芸員の山田志麻子さんのお二人が名を連ねていらした。また、当日の司会を務められた松永康さんも、埼玉県立近代美術館での私の先輩学芸員であり、1997年の「光の化石」の時は、経験の浅い私をサポートしてくださった。
私がまがりなりにも瑛九について何かを調べたり、展覧会を企画したり、文章を書いたりすることができているのは、この日のシンポジウムでお目にかかった方々をはじめ、多くの方々のおかげであることを、感謝の気持ちとともに、深く感じた一日であった。他にも色々と思うところがあり、その全てをここに記すことは到底できないが、無理をしてでも行くことができて良かったと、今は感じている。
それにしても、どうしても、思い出さずにはいられない、瑛九が亡くなった時の都さんの気持ちを。瑛九は1960年3月10日にこの世を去った。その時の思いを綴った都さんの言葉を読み直し、「ミーニョとヒーチョの家」での二人の姿に思いを馳せる。
「悲しい時、苦しい時、嬉しい時、2人してエスペラントの歌をうたってきました。エス語を愛した彼はまたとても犬・猫・動物全般を愛しました。私供の犬・猫はエス語以外は絶対に理解することができず、友人達をおどろかせ、笑わせていました。(中略)彼は動物を愛し、静かにアトリエで絵を描き、疲れると庭に出て私の育てた花の虫をとったり枯葉をとったり、犬と遊んだり…… ただただ絵を描くために此の世に生れて来た人でした。趣味といえば2人してラジオの流してくれるスポーツ放送に耳を傾けたのしむ位でした。
いまの私にはとてもこれ以上 Hiĉjoのことを書きつづけて行くことは、非常な努力です。いまだに彼の死を実感として感じることができず、それを納得させようとする気持ちにもならず、彼のことを書くとすれば、私は一生かかっても書きつくすことはできないでしょう。私はいま彼の死から逃れよう逃れようと思う気持ちと、はっきりと彼の死を納得させようとする気持ちでなやんでいます。(後略)」(出典:『生誕100年記念 瑛九展』宮崎県立美術館ほか、2011年、51頁、資2-19;杉田都「Kara mia Hiĉjo」『ラ・ジョーヨ』44号、1960年、2頁。)
「湯浅コレクション」より 《少女》 1954年
「ミーニョとヒーチョの家」を初めて訪れた時の記憶が脳裏に浮かび、都さんの気丈な姿に、いまでも心を打たれるが、その記憶が、私に覚醒を促す。「湯浅コレクション」の作品群を見た時と同じことが起きている。この連載の第1回に記したように、今年、2023年の6月、ときの忘れもので開催された「第33回瑛九展・湯浅コレクション」を見た時、私の中で、何かが覚醒した。その覚醒は、この世界に生きている私の現実とは別な次元で、私に対して、書かねばならないと告げていた。
その経験と同じように、シンポジウム「瑛九再考」を契機として、初めてお目にかかった時の都さんの姿を思い出し、再び、私の中で、何かが覚醒した。その覚醒が原動力となり、こうして、私は、書くことができているのだと実感する。ニュー・オーダーの「Avalanche」の長いエンディングで目を閉じ、「Your Silent Face」を聴きながら瑛九と都さんの死について思いを馳せる……。しかし、いつまでも目を閉じているわけにはいかない。「湯浅コレクション」の作品群が、記憶の中の都さんが、私を覚醒させ、私の目を開き、私に告げている、後悔する前に、書かなければならない、と。
「湯浅コレクション」については、ギャラリーによる「第33回瑛九展・湯浅コレクション」の紹介と、この展覧会のカタログに収録されている小林美紀さんの論考「10代で「瑛九」と出会った湯浅英夫」を参照いただきたい。この連載では、今回の第5回から、「湯浅コレクション」に含まれる瑛九のフォト・デッサンを、一点ずつ取り上げることになる。それぞれの作品についての具体的な記述にとどまらず、自由に思考を展開し、フォト・デッサンの射程の広さと深さを、様々な面から論じてみたい。
さて、今回取り上げる一点は、《少女》と題された、1954年制作のフォト・デッサンである(fig.1)。浦和での生活にも慣れ、瑛九が制作意欲をみなぎらせていた時期である。デモクラート美術家協会の活動も盛んであり、瑛九を慕う若い芸術家たちが「ミーニョとヒーチョの家」を訪れ、瑛九そして都さんと交流を深めたことだろう。
「湯浅コレクション」は質の高い作品で構成されているが、この作品は、とてもシンプルなスタイルであり、瑛九のフォト・デッサンの中では、珍しいタイプの作品である。そして、その特徴こそが、最初にこの作品を紹介する理由のひとつでもある。2013年のギャラリー・トークにおいて、マトリクスを用いて解析を試みたように、瑛九は様々な技法を駆使し、同時に複数の技法を組み合わせて制作することを得意としていた。それらの技法の中には、あまり馴染みのない技法や瑛九が自ら編み出した技法なども含まれている。その上で、複数の技法が組み合わされて用いられることが多く、瑛九のフォト・デッサンは、その技法を読み解くことがきわめて難しい。

fig.1 《少女》 1954年
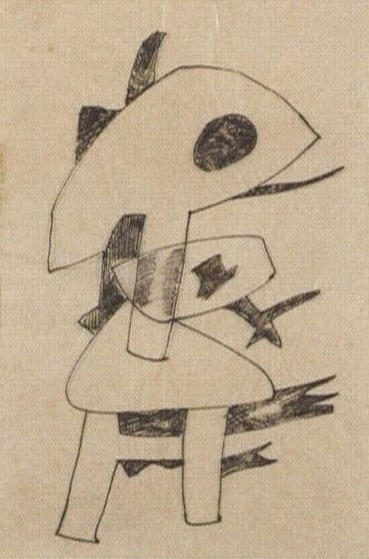
fig.2 《フォト・デッサン型紙》 1953-54年 個人蔵
そのような特徴をふまえると、この《少女》という作品は、ひとつの技法によって制作されており、制作に用いられた型紙(fig.2)も現存しており、制作の工程を明確にすることができる珍しい作例といえる。具体的に示すならば、透明なセロファンにペンで描画された型紙(fig.2) を、印画紙の上に密着するように配置し、光をあてることによって、印画紙の上に、セロファンとは明暗が反転した画像が出現する。瑛九がよく用いる手法であるが、通常は、そこに型紙や様々な材料を組み合わせ、複雑な効果を湛えた画面が出現することが多い。だが、この作品は、セロファンに施された黒の描線が、焼き付けによって白い線として印画紙の上に出現する、極めて明快な制作工程を示している。
画像を成立させる原理に注目すると、描画が施された透明なセロファンを「版」として、密着焼き付けによって画像が印画紙に転写されており、その工程は、版画の原理と同じであることがわかる。版画との違いは、画像の転写が光によって果たされる点である。ここまでお読みいただければ、この技法と近いある技法を思い出す方もいらっしゃるのではないだろうか。そう、「クリシェ=ヴェール」である。
「クリシェ=ヴェール」という用語には馴染みのない方が多いかもしれないが、ガラスを用いて描いた原板を、光によって印画紙に転写する技法である。この技法によって制作された作品を見てみると、エッチングに近い感覚を示すことが比較的多い。その工程を簡略に説明すると、以下のとおりである。
1:ガラス板の上に不透明な塗膜をひく。
2:黒く仕上げたい部分を先の尖った道具を使って塗膜を掻きおとし、透明なガラス板を露出させる。
3:この原板を印画紙に焼きつける。
このように、クリシェ=ヴェールは、直接的な描画がなされるという点では「絵画・素描」であり、描画が施された原板を転写する原理においては「版画」であり、光によって印画紙に画像が定着されるという面に注目すれば「写真」である。瑛九の《少女》の場合は、上記の工程において、ガラスではなく透明なセロファンが用いられており、そのセロファンに直接、描画を施している。そのため、クリシェ=ヴェールとは明暗が反転しているが、透過性のある薄い面への描画が光によって転写される原理は共通している。
クリシェ=ヴェールは、写真に関わる技術が開拓される途上の1830年代末頃に生まれ、1850-60年代のフランス、イギリス、アメリカなどで主に試みられている。フランスでは、印象派に先行するバルビゾン派の画家を中心に流行がみられたが、特にカミーユ・コローのクリシェ=ヴェールはとても魅力的である。その後、写真技術が発展するに従い、一過性の技法とみなされ、技法としては衰退してしまう。だが、その原理には独自の魅力があり、20世紀に入ると、パウル・クレー、マックス・エルンスト、パブロ・ピカソ、ブラッサイらが、クリシェ=ヴェールを試みるようになる。さらに、現代美術の領域ではロバート・ラウシェンバーグがこの技法を試みている。
フロッタージュやフォトグラムが試みられたシュルレアリスムの時代にクリシェ=ヴェールが注目されたのであれば、技法の開拓に貪欲な瑛九が、この技法と近い原理によって作品を制作したとしても、何の不思議もない。ここで、私が注目したいのは、瑛九のフォト・デッサンは、引き算をすることによって、その制作を支える原理的な技法が明らかになるのではないか、ということである。
仮に、この作品の制作に用いられたfig.2の透明セロファンに、瑛九が得意とする型紙が組み合わされたり、瑛九のフォト・デッサンによく用いられるレースや針金などのモチーフも配置されたりすれば、完成する作品の画像は複雑に入り組んだ構成になり、その明暗の階調も複雑なものとなるだろう。当然ながら、完成した画像から制作の工程や原理を正確に導き出すことは容易ではなくなる。このような方法で制作された場合、その技法に注目すると、フォトグラムとクリシェ=ヴェールの応用技法に、瑛九の特徴である型紙の使用も組み合わされた技法、となるだろうか。
このように見てくると、《少女》は、瑛九のフォト・デッサンの特徴となっている複合的な技法から、クリシェ=ヴェールと共通する透過性のある素材を活用した原理以外の手法を取り去った時に出現するタイプの作品と言えるのである。このことを手がかりに、複雑極まる瑛九のフォト・デッサンの技法を、さらに具体的に論じてみたいのだが、そのことは、次回以降の課題としたい。
Elegia
いま、この原稿を書き終えたのは、2023年11月24日(この連載第5回の公開は2024年1月24日)。ほどなく取り壊されると伝えられている「ミーニョとヒーチョの家」への思いと、瑛九が亡くなった時の都さんの言葉が重なり、胸が締めつけられる。フェードアウトしてゆく「Your Silent Face」と入れ替わるように、静かに遠くから響いてくるのは、ニュー・オーダーの「Elegia」、そう、イアン・カーティスへの追悼曲。ならば、この際、アルバム『Low Life』(1985)収録の5分バージョンに続けて、18分のフル・バージョンも響かせよう、「ミーニョとヒーチョの家」への「Elegia=挽歌」として。
(うめづ げん)
■梅津 元
1966年神奈川県生まれ。1991年多摩美術大学大学院美術研究科修了。専門は芸術学。美術、写真、映像、音楽に関わる批評やキュレーションを中心に領域横断的な活動を展開。主なキュレーション:「DE/construct: Updating Modernism」NADiff modern & SuperDeluxe(2014)、「トランス/リアル-非実体的美術の可能性」ギャラリーαM(2016-17)など。1991年から2021年まで埼玉県立近代美術館学芸員 。同館における主な企画(共同企画を含む):「1970年-物質と知覚 もの派と根源を問う作家たち」(1995)、「ドナルド・ジャッド 1960-1991」(1999)、「プラスチックの時代|美術とデザイン」(2000)、「アーティスト・プロジェクト:関根伸夫《位相-大地》が生まれるまで」(2005)、「生誕100年記念 瑛九展」(2011)、「版画の景色-現代版画センターの軌跡」(2018)、「DECODE/出来事と記録-ポスト工業化社会の美術」(2019)など。
・梅津元のエッセイ「瑛九-フォト・デッサンの射程」。次回更新は2024年2月24日を予定しています。どうぞお楽しみに。
●本日のお勧め作品は、瑛九です。

《題不詳》
フォト・デッサン
27.4×21.8cm
こちらの作品の見積り請求、在庫確認はこちらから
※お問合せには、必ず「件名」「お名前」「連絡先(住所)」を明記してください。
●ときの忘れものの建築は阿部勤先生の設計です。

建築空間についてはWEBマガジン<コラージ2017年12月号18~24頁>に特集されています。
〒113-0021 東京都文京区本駒込5丁目4の1 LAS CASAS
TEL: 03-6902-9530、FAX: 03-6902-9531
E-mail:info@tokinowasuremono.com
http://www.tokinowasuremono.com/
営業時間=火曜~土曜の平日11時~19時。日・月・祝日は休廊。
JR及び南北線の駒込駅南口から約8分です。
第5回「Just silence ... Just nothing ...-第33回瑛九展・湯浅コレクション(その1)」
梅津 元
Just silence ... Just nothing ...ニュー・オーダーのセカンド・アルバム『Power, Corruption & Lies』(1983)のB面の最初を飾る「Your Silent Face」の印象的なフレーズが私の耳に届けられ、ふと、私を瑛九に導いてくれた方を思い出す。瑛九の多面的な活動を、レコード盤のA面とB面の関係に喩えてみせた人だから。A面が終わり、レコード盤を裏返し、B面をセットする。チリチリとした静寂の裂け目から射し込む光のように、この曲が静かに流れ始めると、時折、瑛九の《田園》を思い出す。虚空に放たれる「Just silence ...」、「Just nothing ...」、過ぎた日々を彷徨うかのような、Your Silent Face。
2023年11月12日、シンポジウム「瑛九再考」
いま、この原稿を書いているのは、2023年11月16日。ただ、例によってニュー・オーダーの楽曲の助けを借りた上述のイントロは、10月22日に書いている。その時、ほどなく、私を瑛九に導いてくれた方、すなわち、埼玉県立近代美術館での私の先輩学芸員である大久保静雄さんにお目にかかる機会が訪れるとは、予想できていなかった。
事の次第は、次のとおりである。「さいたま国際芸術祭2023」の関連プログラムとして「創発inさいたま」が立案した「瑛九再考」というシンポジウムの準備中、浦和にある「瑛九のアトリエ」が取り壊される危機に瀕していることが判明したという。去る11月12日、浦和において開催されたシンポジウム「瑛九再考」において、この件に関する経緯と現状が報告され、多くの登壇者が、それぞれの立場からの報告、提言、発信を行った。大久保さんとは、このシンポジウムの会場近くで遭遇したのだった。
この連載の第2回から第4回において、ようやく記録を公開することができた2013年のギャラリー・トークでは、瑛九の活動の諸相を、マトリクスを用いて解析することを試みた。その際、まず、「マトリクスA=絵画のマトリクス」と「マトリクスB=写真のマトリクス」という設定を考えた。そのアイデアは、2011年の「生誕100年記念 瑛九展」の企画段階において、大久保さんが、瑛九の活動をレコード盤のA面とB面の関係になぞらえてとらえるという、極めて示唆に富む提案をされたことに刺激されたものである。だから、10年前のギャラリー・トークの記録公開に取り組んでいる私にとって、そのギャラリー・トークの原点となるアイデアに示唆を与えてくださった大久保さんと、このタイミングでお会いできることに、深い感慨を覚えたのである。
そのシンポジウムのことは、いずれ主催者側がしかるべき記録をとりまとめて公開してくれるのではないかと思われるため、ここでは言及しない。ただ、この日、シンポジウムの最後に発言を求められた際、時間的な制約から、断片的な発言となってしまったため、シンポジウムの参加者やこの連載の読者と共有したい事柄を、ここに記しておきたい。
まず、「瑛九のアトリエ」という呼び方に、少し戸惑いを感じる。瑛九が制作をした場所であるから、アトリエという呼び方をするのは間違いではない。しかし、あの家は、まず、何よりも、瑛九と瑛九夫人の都さんの、二人の生活の場であったはずだ。そして、瑛九は、都さんとの生活の場において、制作を続けていた。だから、あの家は、「瑛九と都さんの家」と呼んだ方がいい。さらに、瑛九は都さんのことを「ミーニョ」と、都さんは瑛九のことを「ヒーチョ」と、エスペラントの愛称で呼んでいたという(「ヒーチョ」は瑛九の本名・杉田秀夫に由来するのだろう)。そのことをふまえて、あの家を、私は「ヒーチョとミーニョの家」と呼びたいと思う。そこまでは、当日、話すことができた。
だが、ここで、もうひとつ進めて、二人の名前の順番を入れ替え、この家を「ミーニョとヒーチョの家」と呼んでみたい気がしてきた。「ミーニョ」こと都さんが先にくるのは、生活という面においては、都さんが切り盛りをしていた訳であり、その生活の基盤があってこそ、瑛九は制作に集中することができたはずだからである。何より、瑛九がこの家で生活し制作に打ち込んだ期間は10年に満たないが、都さんは瑛九の没後、50年以上、この家での生活を続けたのだ。
瑛九の生活と制作を支え、瑛九没後も長きに渡ってこの家と瑛九の作品を守り続けた都さんへの敬意を表し、この家を「ミーニョとヒーチョの家」と呼びたいと思う。シンポジウムの当日は、初めてこの家を訪れた日に都さんから伺った話を手短に報告することしかできなかった。そのため、以下では、シンポジウムの参加者やこの連載の読者と共有したい事柄を、記しておきたい。
1997年4月24日、「ミーニョとヒーチョの家」、都さん
私が「ミーニョとヒーチョの家」を初めて訪れたのは、1997年4月24日のことである。この年の6月から、埼玉県立近代美術館において、企画展「光の化石-瑛九とフォトグラムの世界」が開催されることになっていた。私はその展覧会を担当しており、大久保さんから、都さんに挨拶に行くようにと言われていたのである。当日は、当時の学芸部長の水野隆さん、大久保さん、筑波大学の五十殿利治さん、それに私という、4名での訪問となった。五十殿さんは、刊行準備が進められていた『瑛九作品集』(日本経済新聞社)に収録される論文を執筆されていらして、都さんにご挨拶をしたいと、大久保さんに連絡を入れていらしたとのことであった。
都さんに負担をかけないために、一緒に訪問するという段取りになったのであるが、当日、極度の緊張が私を襲ったことは言うまでもない。それは、私と同じく、この日、初めて都さんにお目にかかることになる五十殿さんも同様であったようである。都さんにご挨拶をすませ、五十殿さんは『瑛九作品集』のことをお話されて、私は「光の化石」のことを説明し、その後は、都さんのお話を伺う貴重な時間を過ごした。その途中、五十殿さんは、腰が痛いので腰を伸ばしてきますと、一度、席を外され、庭に出られて、腰を伸ばしていらした。それだけ緊張されていらしたのだ。
その時、ああ、五十殿さんでもあれだけ緊張するのだから、自分が極度の緊張に襲われるのも無理はないなと思ったのである。もちろん、私も、緊張を少しでもほぐすべく、そのタイミングを逃さず、五十殿さんに続いて庭に出て、凝り固まった体をほぐそうとした。そして、ああ、点描の絵を庭に出してその絵に囲まれたいと瑛九が語った、その庭に、いま、自分が立っているのだと、緊張の只中にありながら、深い感慨に浸ったことも、その日の忘れ難い思い出である。
いま、手元に、「光の化石」の時のノートがある。このノートには、1997年4月24日に都さんから伺った話の要点がメモしてある。極度の緊張の中でも、頭の中でテープレコーダーに録音するように、都さんのお話を、一言残らず記憶しておこうと必死だった。だから、同行した方々と別れて一人になってすぐ、頭の中のテープレコーダーを再生するようにして、都さんの口調や身振り手振りを思い出しながら、急いでメモを記したのである。
普段、ノートのメモを読み返そうとすると、自分でも読めないほどひどい字なのであるが、この時の都さんのお話を記したメモは、どういうわけか、比較的まともで、十分に読むことができる。「ミーニョとヒーチョの家」で都さんと対面している時の緊張感が持続していて、その緊張の中で、メモを書いたのだろうか。あるいは、いつか、都さんが話してくださったことを思い出せなくなってしまった時に、このメモが読めなくならないように、きちんと読める字で書かなければ、それだけ大事な記録なのだと、自分に言い聞かせたのだろうか。何も思い出せないが、メモがあってよかった、ただ、そう思う。
都さんが話してくださったこと
以下、都さんがお話してくださったことを、書いておきたい。なお、シンポジウム当日は、時間の制約から、以下の都さんのお話の7~8割を読み上げるにとどめた。
・瑛九は命を縮めて制作に打ち込んでいた。
・浦和から外へ出たことは極めて少ない。
・展覧会のオープニングのために背広を着てほしいと言われたが、持っていなかった。
都さんが妹夫婦に相談して調達したが、一回しか着なかった。
・絵の具がついたままの服で外出し、そのまますぐ帰る。着替えると制作中のイメージがとんでしまうから。
・銅版や印画紙を買いに神田へ行くのも都さんだった。
・瀧口修造によるタケミヤ画廊の展覧会の時も、画廊につめるのは都さんで、瑛九は制作していた。
・人づきあいは苦手で、芸術論以外は会話しなかった。
・走ると手足が一緒になったのを駅のホームで見た。
・運動神経は良くなかった。
・自転車に乗れず、移動すると、一緒に倒れた。
・橋を渡ると「飛び込め」という強迫観念があって、ひとりで橋を渡れなかった。車か、付き添いが必要。
・傘をさしても肩にかけてしまい、雨にぬれていた。
・浦和の家は都さんがみつけた。かやぶきの家だった。
・当時2軒しかなく、田んぼ、林だった。
・富本憲吉の知り合いの石井さんという陶芸の人の家だったらしい。
・犬、猫を飼った(宮崎での話)。
・浦和でも犬を飼った、にわとりも。
・黄色は瑛九において重要な色である。
この日のシンポジウムは、感慨深いものとなった。それは、会場の入口で、私を瑛九に導いてくださった大久保さんとお会いし、一緒に会場に入り、隣の席でシンポジウムを聞くことになったからである。登壇者には、埼玉県立近代美術館での私の後輩学芸員である吉岡知子さんと、2011年の「生誕100年記念 瑛九展」の時に苦楽をともにしたうらわ美術館学芸員の山田志麻子さんのお二人が名を連ねていらした。また、当日の司会を務められた松永康さんも、埼玉県立近代美術館での私の先輩学芸員であり、1997年の「光の化石」の時は、経験の浅い私をサポートしてくださった。
私がまがりなりにも瑛九について何かを調べたり、展覧会を企画したり、文章を書いたりすることができているのは、この日のシンポジウムでお目にかかった方々をはじめ、多くの方々のおかげであることを、感謝の気持ちとともに、深く感じた一日であった。他にも色々と思うところがあり、その全てをここに記すことは到底できないが、無理をしてでも行くことができて良かったと、今は感じている。
それにしても、どうしても、思い出さずにはいられない、瑛九が亡くなった時の都さんの気持ちを。瑛九は1960年3月10日にこの世を去った。その時の思いを綴った都さんの言葉を読み直し、「ミーニョとヒーチョの家」での二人の姿に思いを馳せる。
「悲しい時、苦しい時、嬉しい時、2人してエスペラントの歌をうたってきました。エス語を愛した彼はまたとても犬・猫・動物全般を愛しました。私供の犬・猫はエス語以外は絶対に理解することができず、友人達をおどろかせ、笑わせていました。(中略)彼は動物を愛し、静かにアトリエで絵を描き、疲れると庭に出て私の育てた花の虫をとったり枯葉をとったり、犬と遊んだり…… ただただ絵を描くために此の世に生れて来た人でした。趣味といえば2人してラジオの流してくれるスポーツ放送に耳を傾けたのしむ位でした。
いまの私にはとてもこれ以上 Hiĉjoのことを書きつづけて行くことは、非常な努力です。いまだに彼の死を実感として感じることができず、それを納得させようとする気持ちにもならず、彼のことを書くとすれば、私は一生かかっても書きつくすことはできないでしょう。私はいま彼の死から逃れよう逃れようと思う気持ちと、はっきりと彼の死を納得させようとする気持ちでなやんでいます。(後略)」(出典:『生誕100年記念 瑛九展』宮崎県立美術館ほか、2011年、51頁、資2-19;杉田都「Kara mia Hiĉjo」『ラ・ジョーヨ』44号、1960年、2頁。)
「湯浅コレクション」より 《少女》 1954年
「ミーニョとヒーチョの家」を初めて訪れた時の記憶が脳裏に浮かび、都さんの気丈な姿に、いまでも心を打たれるが、その記憶が、私に覚醒を促す。「湯浅コレクション」の作品群を見た時と同じことが起きている。この連載の第1回に記したように、今年、2023年の6月、ときの忘れもので開催された「第33回瑛九展・湯浅コレクション」を見た時、私の中で、何かが覚醒した。その覚醒は、この世界に生きている私の現実とは別な次元で、私に対して、書かねばならないと告げていた。
その経験と同じように、シンポジウム「瑛九再考」を契機として、初めてお目にかかった時の都さんの姿を思い出し、再び、私の中で、何かが覚醒した。その覚醒が原動力となり、こうして、私は、書くことができているのだと実感する。ニュー・オーダーの「Avalanche」の長いエンディングで目を閉じ、「Your Silent Face」を聴きながら瑛九と都さんの死について思いを馳せる……。しかし、いつまでも目を閉じているわけにはいかない。「湯浅コレクション」の作品群が、記憶の中の都さんが、私を覚醒させ、私の目を開き、私に告げている、後悔する前に、書かなければならない、と。
「湯浅コレクション」については、ギャラリーによる「第33回瑛九展・湯浅コレクション」の紹介と、この展覧会のカタログに収録されている小林美紀さんの論考「10代で「瑛九」と出会った湯浅英夫」を参照いただきたい。この連載では、今回の第5回から、「湯浅コレクション」に含まれる瑛九のフォト・デッサンを、一点ずつ取り上げることになる。それぞれの作品についての具体的な記述にとどまらず、自由に思考を展開し、フォト・デッサンの射程の広さと深さを、様々な面から論じてみたい。
さて、今回取り上げる一点は、《少女》と題された、1954年制作のフォト・デッサンである(fig.1)。浦和での生活にも慣れ、瑛九が制作意欲をみなぎらせていた時期である。デモクラート美術家協会の活動も盛んであり、瑛九を慕う若い芸術家たちが「ミーニョとヒーチョの家」を訪れ、瑛九そして都さんと交流を深めたことだろう。
「湯浅コレクション」は質の高い作品で構成されているが、この作品は、とてもシンプルなスタイルであり、瑛九のフォト・デッサンの中では、珍しいタイプの作品である。そして、その特徴こそが、最初にこの作品を紹介する理由のひとつでもある。2013年のギャラリー・トークにおいて、マトリクスを用いて解析を試みたように、瑛九は様々な技法を駆使し、同時に複数の技法を組み合わせて制作することを得意としていた。それらの技法の中には、あまり馴染みのない技法や瑛九が自ら編み出した技法なども含まれている。その上で、複数の技法が組み合わされて用いられることが多く、瑛九のフォト・デッサンは、その技法を読み解くことがきわめて難しい。

fig.1 《少女》 1954年
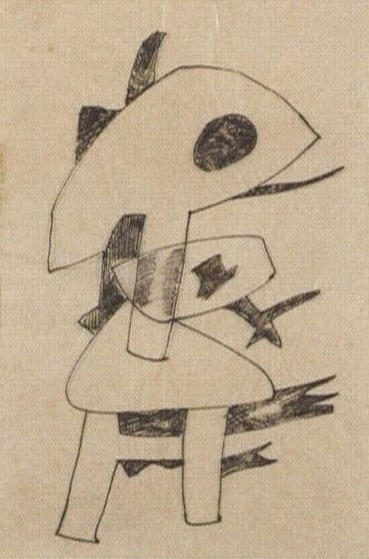
fig.2 《フォト・デッサン型紙》 1953-54年 個人蔵
そのような特徴をふまえると、この《少女》という作品は、ひとつの技法によって制作されており、制作に用いられた型紙(fig.2)も現存しており、制作の工程を明確にすることができる珍しい作例といえる。具体的に示すならば、透明なセロファンにペンで描画された型紙(fig.2) を、印画紙の上に密着するように配置し、光をあてることによって、印画紙の上に、セロファンとは明暗が反転した画像が出現する。瑛九がよく用いる手法であるが、通常は、そこに型紙や様々な材料を組み合わせ、複雑な効果を湛えた画面が出現することが多い。だが、この作品は、セロファンに施された黒の描線が、焼き付けによって白い線として印画紙の上に出現する、極めて明快な制作工程を示している。
画像を成立させる原理に注目すると、描画が施された透明なセロファンを「版」として、密着焼き付けによって画像が印画紙に転写されており、その工程は、版画の原理と同じであることがわかる。版画との違いは、画像の転写が光によって果たされる点である。ここまでお読みいただければ、この技法と近いある技法を思い出す方もいらっしゃるのではないだろうか。そう、「クリシェ=ヴェール」である。
「クリシェ=ヴェール」という用語には馴染みのない方が多いかもしれないが、ガラスを用いて描いた原板を、光によって印画紙に転写する技法である。この技法によって制作された作品を見てみると、エッチングに近い感覚を示すことが比較的多い。その工程を簡略に説明すると、以下のとおりである。
1:ガラス板の上に不透明な塗膜をひく。
2:黒く仕上げたい部分を先の尖った道具を使って塗膜を掻きおとし、透明なガラス板を露出させる。
3:この原板を印画紙に焼きつける。
このように、クリシェ=ヴェールは、直接的な描画がなされるという点では「絵画・素描」であり、描画が施された原板を転写する原理においては「版画」であり、光によって印画紙に画像が定着されるという面に注目すれば「写真」である。瑛九の《少女》の場合は、上記の工程において、ガラスではなく透明なセロファンが用いられており、そのセロファンに直接、描画を施している。そのため、クリシェ=ヴェールとは明暗が反転しているが、透過性のある薄い面への描画が光によって転写される原理は共通している。
クリシェ=ヴェールは、写真に関わる技術が開拓される途上の1830年代末頃に生まれ、1850-60年代のフランス、イギリス、アメリカなどで主に試みられている。フランスでは、印象派に先行するバルビゾン派の画家を中心に流行がみられたが、特にカミーユ・コローのクリシェ=ヴェールはとても魅力的である。その後、写真技術が発展するに従い、一過性の技法とみなされ、技法としては衰退してしまう。だが、その原理には独自の魅力があり、20世紀に入ると、パウル・クレー、マックス・エルンスト、パブロ・ピカソ、ブラッサイらが、クリシェ=ヴェールを試みるようになる。さらに、現代美術の領域ではロバート・ラウシェンバーグがこの技法を試みている。
フロッタージュやフォトグラムが試みられたシュルレアリスムの時代にクリシェ=ヴェールが注目されたのであれば、技法の開拓に貪欲な瑛九が、この技法と近い原理によって作品を制作したとしても、何の不思議もない。ここで、私が注目したいのは、瑛九のフォト・デッサンは、引き算をすることによって、その制作を支える原理的な技法が明らかになるのではないか、ということである。
仮に、この作品の制作に用いられたfig.2の透明セロファンに、瑛九が得意とする型紙が組み合わされたり、瑛九のフォト・デッサンによく用いられるレースや針金などのモチーフも配置されたりすれば、完成する作品の画像は複雑に入り組んだ構成になり、その明暗の階調も複雑なものとなるだろう。当然ながら、完成した画像から制作の工程や原理を正確に導き出すことは容易ではなくなる。このような方法で制作された場合、その技法に注目すると、フォトグラムとクリシェ=ヴェールの応用技法に、瑛九の特徴である型紙の使用も組み合わされた技法、となるだろうか。
このように見てくると、《少女》は、瑛九のフォト・デッサンの特徴となっている複合的な技法から、クリシェ=ヴェールと共通する透過性のある素材を活用した原理以外の手法を取り去った時に出現するタイプの作品と言えるのである。このことを手がかりに、複雑極まる瑛九のフォト・デッサンの技法を、さらに具体的に論じてみたいのだが、そのことは、次回以降の課題としたい。
Elegia
いま、この原稿を書き終えたのは、2023年11月24日(この連載第5回の公開は2024年1月24日)。ほどなく取り壊されると伝えられている「ミーニョとヒーチョの家」への思いと、瑛九が亡くなった時の都さんの言葉が重なり、胸が締めつけられる。フェードアウトしてゆく「Your Silent Face」と入れ替わるように、静かに遠くから響いてくるのは、ニュー・オーダーの「Elegia」、そう、イアン・カーティスへの追悼曲。ならば、この際、アルバム『Low Life』(1985)収録の5分バージョンに続けて、18分のフル・バージョンも響かせよう、「ミーニョとヒーチョの家」への「Elegia=挽歌」として。
(うめづ げん)
■梅津 元
1966年神奈川県生まれ。1991年多摩美術大学大学院美術研究科修了。専門は芸術学。美術、写真、映像、音楽に関わる批評やキュレーションを中心に領域横断的な活動を展開。主なキュレーション:「DE/construct: Updating Modernism」NADiff modern & SuperDeluxe(2014)、「トランス/リアル-非実体的美術の可能性」ギャラリーαM(2016-17)など。1991年から2021年まで埼玉県立近代美術館学芸員 。同館における主な企画(共同企画を含む):「1970年-物質と知覚 もの派と根源を問う作家たち」(1995)、「ドナルド・ジャッド 1960-1991」(1999)、「プラスチックの時代|美術とデザイン」(2000)、「アーティスト・プロジェクト:関根伸夫《位相-大地》が生まれるまで」(2005)、「生誕100年記念 瑛九展」(2011)、「版画の景色-現代版画センターの軌跡」(2018)、「DECODE/出来事と記録-ポスト工業化社会の美術」(2019)など。
・梅津元のエッセイ「瑛九-フォト・デッサンの射程」。次回更新は2024年2月24日を予定しています。どうぞお楽しみに。
●本日のお勧め作品は、瑛九です。

《題不詳》
フォト・デッサン
27.4×21.8cm
こちらの作品の見積り請求、在庫確認はこちらから
※お問合せには、必ず「件名」「お名前」「連絡先(住所)」を明記してください。
●ときの忘れものの建築は阿部勤先生の設計です。

建築空間についてはWEBマガジン<コラージ2017年12月号18~24頁>に特集されています。
〒113-0021 東京都文京区本駒込5丁目4の1 LAS CASAS
TEL: 03-6902-9530、FAX: 03-6902-9531
E-mail:info@tokinowasuremono.com
http://www.tokinowasuremono.com/
営業時間=火曜~土曜の平日11時~19時。日・月・祝日は休廊。
JR及び南北線の駒込駅南口から約8分です。
コメント