建築家が版画をつくること
磯崎新
建築家でありながら、何故、版画をつくるのか。その問いに答えるには、いくつかの事例を挙げることがいいだろう。
18世紀の建築家は多くのエッチングを残した。ピラネージはそのなかでも、その版画の仕事でとりわけ知られている。彼は建築の設計をやっていたが、実現する機会にめぐまれなかった。ただひとつだけ教会が残っているだけだ。彼を有名にしたのは、むしろ最初は余技のようにはじめた版画である。
そのなかでも、バロックの幻想的な空間を誇張してえがいた牢獄シリーズで、ここにはとうてい実現しそうにもないし、かりに存在してもこれだけの効果を持ちえない、と思えるような空間が表現されている。さらに、古代ローマの都市の復原図では、考古学的事実を想像力がはるかに凌駕し、その壮大さを徹底して印象づけるものとなった。だが、永遠のベストセラーとなったのは、ローマの名跡をうつしたもので、これは今日の観光写真の役割りもした。
そこには2つの役割りが版画に与えられているのが分かるだろう。ひとつは記録である。もうひとつは、彼の幻想が、その描く相手をはるかに超えて、現実には存在しえない空間をアーティストとして造りだしたことである。その背後には、印刷技術の問題もある。この時代の本の挿図は基本的に木版である。そしてエッチングも用いられたが、いわば、版画と今日呼ばれている領域は、いずれも印刷の一部とみられていたことを知っておく必要があろう。
たとえば、いま、私たちは、ルドゥの<L'Architecture Consideree sous le Rapport de L'Art, des Moeurs et de la Legislation>とか、シンケルの<Sammlung Architektonischer Entwurfe>をエッチングでみている。これらは、いずれも幻想性の豊かなデザインであるが、実際に建てようとして描いた図面が基本になっている。そのあるものは実現している。あるものは提案どまりである。あるものは、実現を求める相手なしに、想像だけでえがかれている。彼らは、その図面を、本のかたちで出版しようとした、と考えるべきである。セルリオ、パッラディオ、スカモッティ、いずれも図面を本のために、再整理して、描きなおしている。
いつの間にか、シート状になり箱に収められた本のための図面が、独立して、壁にかけられるようになった。ピラネージの場合は、当初からばらばらに版画としているが、他の建築家のものは、版画状の本で、それが、ときに抜きだされて、版画の扱いをうけたとみるのがいい。
現代の建築家では、ル・コルビュジェの版画が数多く出まわっている。彼は建築家のトレーニングを受けたが、一時は画家になろうとした。ジャンヌレという本名で、オザンファンとともに、ピュリズムの宣言をした程だから、画家と建築家の双方を同時に兼ねようとしたことは明らかで、その点ではルネサンスの芸術家、ラファエロ、ミケランジェロ、ジュリオ・ロマーノなどと共通した古典的なタイプの芸術家である。彼は午前中は自宅の上階にあったアトリエで絵を描き、午後からは建築事務所で仕事をした。晩年になって、数多くのリトグラフをつくった。壁画として、自作を直接拡大したり、タピストリーに織ったりした。彼は、対象を独自に変形させるスタディを毎日スケッチのかたちでやり、そこで生まれたかたちを、実際の建築のかたちに強く反映させようとした。その点で建築の形態を決定づける予備作業として、彼のデッサンがあったといっていいが、そのとき描く対象は、人物や静物なので、それを独立させて版画がつくられた、といえるかも知れない。
そこで、建築家による版画のタイプを整理すると、次の3つぐらいになる。
① 計画案あるいは実施案として設計された図面を、本として印刷するように、独立した複数のプレートにしてあるもの。
② 現実に実現するというよりも、建築的要素を手がかりにして、想像力をふくらませ、幻想的な空間をえがきだそうとするようなドローイングを、版画のかたちにしたもの。
③ 建築的主題とは無縁に、その予備的なスタディでもあるが、既に独立したひとつのタブローを指向して、それを版画形式にしたもの。
などで、これは、いずれも建築にかかわるドローイングとしてのみ考えておけばいいのだが、それが、複数のものとして版画にされるところは、画家が版画をつくるということと基本的には変らないだろう。すくなくとも、単一のオリジナルとして、作家のアウラとしての手の痕跡が残されているものにたいして、複数につくられる版画は異った機能を持つことは明らかで、建築家の場合、日常作業のなかで、彼はひとつの線を引いても、これが幾度となく他の手によってトレースされてやっと実現するというプロセスが普通であるから、アウラ消滅を気にすることはない。むしろ、他の手を介しながら、拡大され、物質化されるその過程のなかに本来の作業があるといっていい。
ところで、私の場合、いま分類したいずれのケースにもあてはまるのだが、若干異っているとするならば、自分の建築作品を、自分で分析してみせる、その有様を版画にしたてるところであろうか。
決して、空想的な建築を描こうとしているのではない。ましてや、画家としてドローイングしているわけでもない。いずれの主題も、実際に注文があって、かなり長い期間の建築的スタディが行なわれ、ひとつの建築として、デザインの完了したものがあらためてとりあげられている。
建築の宿命は、ひとつの決められた場所に固定されて建設されることである。そこで、土地の精霊といったものとかかわることが多大の議論になるわけだが、そのような土着化をめざした形式を私は必ずしも捜しているのではない。ときに、そのような関係がぴったり生れてくることもあろうが、これはむしろ結果である。建築のコンセプトは、当所その特定の土地から切りはなれている。数々の試みがなされるなかで、地形、敷地の形状、風土、独自の空気、気分、そして季節感にいたるまでが建物の細部にまとわりつきはじめる。それを最大限許容していくことに、私の実務的な関心はあるのだが、いいかえると、この過程は、建築に与えられる純枠形態の、変形過程とみるべきかも知れない。
先に、できあがった自分の建築を、あらためて分析してみる、といったのは、この変形過程を、逆にたどって、当初の原型的イメージに、もういちど還元してみる作業をしていることを指している。
〈還元シリーズ〉と名づけたのは、このような作業に由来する。ここではいままで私が設計した公共的、商業的な建物が、順々にとりあげられている。おそらく、ひとつの建物につき、ひとつだけしかつくられないだろうが、そのいずれもが、建物を発想して、決定的なアイディアとして定着していったときのイメージを、そのままの状態で二次元的な平面上に表現するように意図している。だから設計過程で、これとまったく同じものがスケッチされた、というわけではない。近似的なものは、いくつも描かれている。だが最終的な設計図としておさまる過程で、そのスケッチは、変形を加えられている。同時に、建築は三次元的な立体であり、空間を包含しているのだが、設計の段階では、平面や立面や断面といった、切断された二次元的な図だけを扱っていることが多い。その図が描かれているときに、建築家は、常に三次元的な空間として、それが実寸大に拡張されて実現するときの有様を、想像し読みとる訓練がなされていなければならず、そんな背後の意図を断片的に指示する記符号として図を読むわけだから、建築になじみのない人たちには、とりつきにくいものになっている。そこで、原型に還元されたものを、二次元的な面のうえで立体的な像として再現する手段を構じる必要がうまれる。アクソノメトリックと呼ばれる図法を用いると、平面が立体的にみえる。普通は、30°あるいは45°の斜めからみるので、丁度、源氏物語絵巻などにみられるような、日本の伝統的な吹抜屋台の画法に似ている。それをあえて、90°という垂直にみたまんまで、ここでは描いてある。90°にしたアクソノメトリックは、線猫だけではかなり読みとりにくいけど、これに陰影をつけると立体的に立ちあがってくる。シルクスクリーンで刷ることが実は陰影をつけやすくしているのである。つまり、この印刷過程で、画面はすべて色面に分解されねばならない。だから、エッチングなどの線の集合体のややこしさに較べて、陰影を簡単につけることができる。
アクソノメトリックの特徴は、平面図も立面図も変形することなしに、そのまま組込まれてしまっていることである。相互を連結してしまうだけで立体的な表現へ接近できる。そのために近代になって建築家から愛用されている方式である。平面と立面を同時にみせることは、いいかえると、無限大の焦点距離で、空中から建物を視ている状態になる。鳥瞰図的な視点といっていい。問題は、航空写真でも撮らないかぎり、現実にはこれに似た視点で建物がみえることはないので、むしろ、抽象的で、概念的な表現になってしまうことである。源氏物語絵巻の吹抜屋台は、寝殿造りの室内を、屋根をとりはずして眺め下している。それを神の視点だ、という人もある。住吉天神縁起では、たとえば、雷神などがその一隅に出現する。黒雲にのった雷神は空中にあるわけで、そこから室内を見下しているのはいいが、この雷神も同時に上方から見下ろされる。これは、描法の限界といえるかも知れない。もしこの吹抜屋台の描法の比喩を用いるならば、アクソノメトリックは、視線の生み出すヒエラルキーを解体したあげくに、各部分を均質化して、抽象的な空間のなかに浮かしてしまう、神も人間もかかわらない協約的視点といっていい。必然的に土地や風土の制約は捨象され、独立した抽象形態としてのみ描かれることになる。
それ故に、発生状態にあるイメージを定着するのに適した手法と思える。その段階では、建築は、地形の特性も、生活の臭いも、背後のわい雑な電柱や看板もない。純粋な幾何学性をもった空間や、ひとつの形式としての構造体でしかない。その有様だけをシルクスクリーンで定着する。<還元シリーズ>は、そこで、幾何学的な立体、架構体、そしてプライマリーな色彩、それだけに還元された建築の原始形態なのである。<ヴィッラ・シリーズ>は、住宅だけを扱うことにしている。私の住宅では、これまでバレル・ヴォールトがかなり基本的な共通のモチーフになってきている。そして、居住空間も原則的に、立方体や円筒に基いている。<還元シリーズ>では、部分的に輪郭まで分解する作業をしているが、<ヴィッラ・シリーズ>は、むしろ、輪郭を大事にし、そのなかの空間が暗示されるように心がけている。いいかえると、ここでの住宅は、ひとつの彫刻的なオブジェクトとしてみてもいいという表明である。建物を幾何学的形態に基いて構築することは、私のフォルマリスト的なアプローチの原則でもある。このようにしてえらびだされている形態が、独自に展開して、次々に住居の形式を組みたてていくという、運動過程がみえてくれば、いっそう目的が達せられることになる。
今度、新しくはじめたのに<MOCA#1、#2、#3、>のような、普通の透視図法に基いたシルクスクリーンがある。ここでは、ロサンゼルスという、透明な空気と、激しい太陽の下に置かれる美術館として、インド産の赤砂岩を用いたデザインの意図を的確に表現したいと思ったときに、空を導入することがどうしても必要だと考えた。アクソノメトリックの方式でやると、地面を空中から見下すことになって、決して空はあらわれない。そこで、描法を変えて、普通の地上の視点からみた透視図法を用いることにしたのである。建物は、それでも極端に単純化されて、この建物の基本形である純粋立体幾何学のみが浮びあがるようにしてある。そして、色彩と陰影と、空を強調して、ロサンゼルスの空気を表現することを試みたものである。これはいずれ実物として建ちあがるだろう。そのとき写真がとられたとしても、これとは異ってうつるにちがいない。若干の緑が植えられ、既存の建物にとりまかれ、人や車がうごいているだろう。そんななかに置かれる建物の基本的なイメージが、ここでもやはり抽出されようとしている。
版画の利点は、たったひとつのオリジナルという古典的なアウラの痕跡を越えて、複製され、流通することである。勿論私自身、建物の設計過程でスケッチを大量に残すことがある。だけどこれは製図板のうえで、かたちを捜している過程の断片で、決してみせるためにやっているのではない。むしろ必要なのはそのスケッチをスタッフが描きなおし、建築的な図面にすることである。とすれば、手の痕跡だけで勝負するアーティストとは異って、建築家には、手の痕跡は決定的な重要性を持っていないと考えていい。むしろ、私にとって重要なのは、その作業過程にたちあらわれる建築の基本的概念が、どのように伝達され、実施され、具体的な空間となるかという点である。とすれば、そのアイディアがもっとも的確に表現され、伝達される手段がみつかればいいわけで、そのような図法を開発していくことの方がより大きい課題となる。版画は、ここで生まれた図法を再現し、複製にしてくれる。単一のクライアントだけを相手にし、特定の場所に固定される宿命をもつ建築が、ここで複数化し、より多くの人々の眼にふれることになる。その点においても、版画は、閉ざされたアイディアを開放する役割りもしてくれる。仕事の区切りに、版画をつくるという楽しみもまだこれからも残されている、というわけである。
(いそざき あらた)


『The Prints of Arata Isozaki 1977-1983』所収
発行日:1983年11月4日
発行:現代版画センター
執筆:磯崎新、松岡正剛、八束はじめ
英訳:ドナルド・フィリパイ、木幡和江、南谷覺正
デザイン:横尾忠則
編集:星野治樹
シルクスクリーン刷り:石田了一
銅版画刷り:山村兄弟版画工房

磯崎新「FOLLYー草庵」
1983年 シルクスクリーン(刷り:石田了一)
16×19cm
限定1,500部
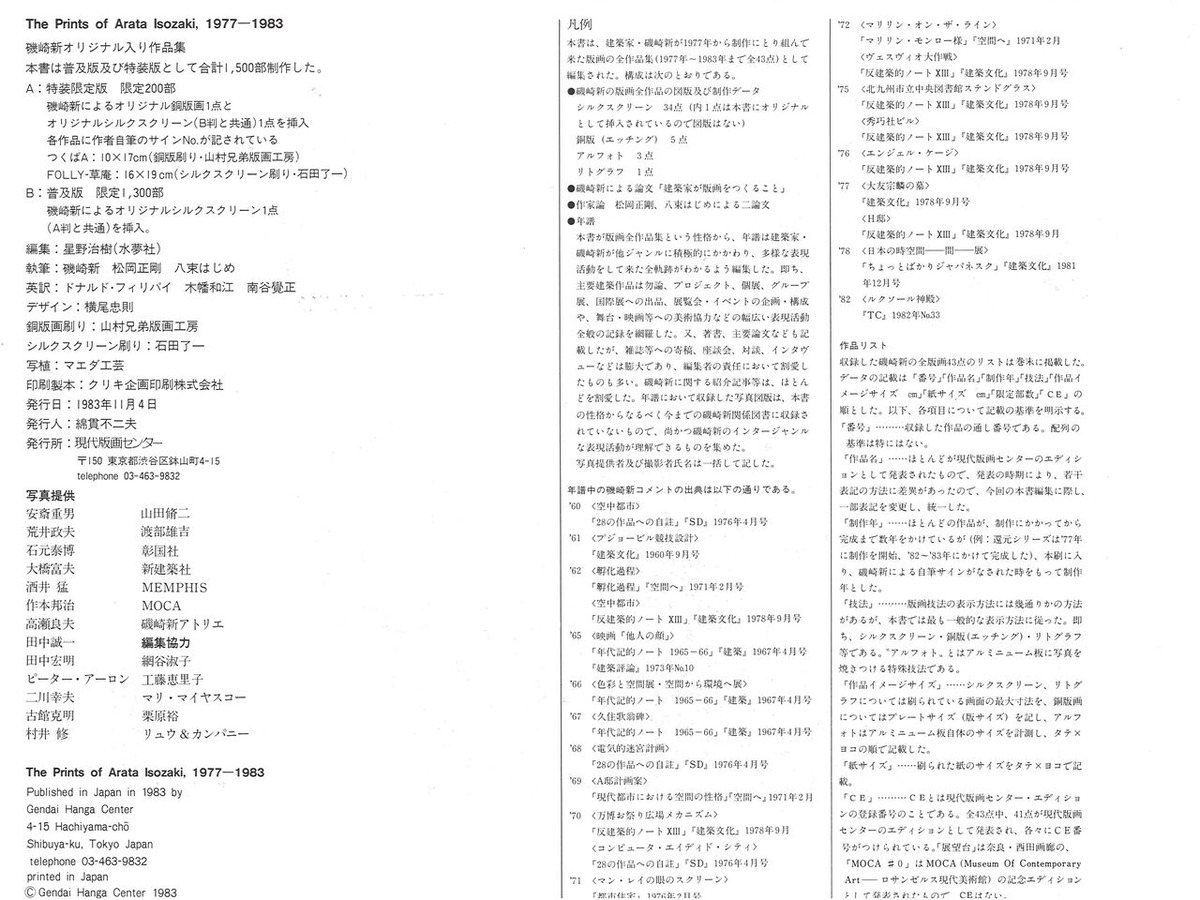 奥付
奥付
磯崎新
建築家でありながら、何故、版画をつくるのか。その問いに答えるには、いくつかの事例を挙げることがいいだろう。
18世紀の建築家は多くのエッチングを残した。ピラネージはそのなかでも、その版画の仕事でとりわけ知られている。彼は建築の設計をやっていたが、実現する機会にめぐまれなかった。ただひとつだけ教会が残っているだけだ。彼を有名にしたのは、むしろ最初は余技のようにはじめた版画である。
そのなかでも、バロックの幻想的な空間を誇張してえがいた牢獄シリーズで、ここにはとうてい実現しそうにもないし、かりに存在してもこれだけの効果を持ちえない、と思えるような空間が表現されている。さらに、古代ローマの都市の復原図では、考古学的事実を想像力がはるかに凌駕し、その壮大さを徹底して印象づけるものとなった。だが、永遠のベストセラーとなったのは、ローマの名跡をうつしたもので、これは今日の観光写真の役割りもした。
そこには2つの役割りが版画に与えられているのが分かるだろう。ひとつは記録である。もうひとつは、彼の幻想が、その描く相手をはるかに超えて、現実には存在しえない空間をアーティストとして造りだしたことである。その背後には、印刷技術の問題もある。この時代の本の挿図は基本的に木版である。そしてエッチングも用いられたが、いわば、版画と今日呼ばれている領域は、いずれも印刷の一部とみられていたことを知っておく必要があろう。
たとえば、いま、私たちは、ルドゥの<L'Architecture Consideree sous le Rapport de L'Art, des Moeurs et de la Legislation>とか、シンケルの<Sammlung Architektonischer Entwurfe>をエッチングでみている。これらは、いずれも幻想性の豊かなデザインであるが、実際に建てようとして描いた図面が基本になっている。そのあるものは実現している。あるものは提案どまりである。あるものは、実現を求める相手なしに、想像だけでえがかれている。彼らは、その図面を、本のかたちで出版しようとした、と考えるべきである。セルリオ、パッラディオ、スカモッティ、いずれも図面を本のために、再整理して、描きなおしている。
いつの間にか、シート状になり箱に収められた本のための図面が、独立して、壁にかけられるようになった。ピラネージの場合は、当初からばらばらに版画としているが、他の建築家のものは、版画状の本で、それが、ときに抜きだされて、版画の扱いをうけたとみるのがいい。
現代の建築家では、ル・コルビュジェの版画が数多く出まわっている。彼は建築家のトレーニングを受けたが、一時は画家になろうとした。ジャンヌレという本名で、オザンファンとともに、ピュリズムの宣言をした程だから、画家と建築家の双方を同時に兼ねようとしたことは明らかで、その点ではルネサンスの芸術家、ラファエロ、ミケランジェロ、ジュリオ・ロマーノなどと共通した古典的なタイプの芸術家である。彼は午前中は自宅の上階にあったアトリエで絵を描き、午後からは建築事務所で仕事をした。晩年になって、数多くのリトグラフをつくった。壁画として、自作を直接拡大したり、タピストリーに織ったりした。彼は、対象を独自に変形させるスタディを毎日スケッチのかたちでやり、そこで生まれたかたちを、実際の建築のかたちに強く反映させようとした。その点で建築の形態を決定づける予備作業として、彼のデッサンがあったといっていいが、そのとき描く対象は、人物や静物なので、それを独立させて版画がつくられた、といえるかも知れない。
そこで、建築家による版画のタイプを整理すると、次の3つぐらいになる。
① 計画案あるいは実施案として設計された図面を、本として印刷するように、独立した複数のプレートにしてあるもの。
② 現実に実現するというよりも、建築的要素を手がかりにして、想像力をふくらませ、幻想的な空間をえがきだそうとするようなドローイングを、版画のかたちにしたもの。
③ 建築的主題とは無縁に、その予備的なスタディでもあるが、既に独立したひとつのタブローを指向して、それを版画形式にしたもの。
などで、これは、いずれも建築にかかわるドローイングとしてのみ考えておけばいいのだが、それが、複数のものとして版画にされるところは、画家が版画をつくるということと基本的には変らないだろう。すくなくとも、単一のオリジナルとして、作家のアウラとしての手の痕跡が残されているものにたいして、複数につくられる版画は異った機能を持つことは明らかで、建築家の場合、日常作業のなかで、彼はひとつの線を引いても、これが幾度となく他の手によってトレースされてやっと実現するというプロセスが普通であるから、アウラ消滅を気にすることはない。むしろ、他の手を介しながら、拡大され、物質化されるその過程のなかに本来の作業があるといっていい。
ところで、私の場合、いま分類したいずれのケースにもあてはまるのだが、若干異っているとするならば、自分の建築作品を、自分で分析してみせる、その有様を版画にしたてるところであろうか。
決して、空想的な建築を描こうとしているのではない。ましてや、画家としてドローイングしているわけでもない。いずれの主題も、実際に注文があって、かなり長い期間の建築的スタディが行なわれ、ひとつの建築として、デザインの完了したものがあらためてとりあげられている。
建築の宿命は、ひとつの決められた場所に固定されて建設されることである。そこで、土地の精霊といったものとかかわることが多大の議論になるわけだが、そのような土着化をめざした形式を私は必ずしも捜しているのではない。ときに、そのような関係がぴったり生れてくることもあろうが、これはむしろ結果である。建築のコンセプトは、当所その特定の土地から切りはなれている。数々の試みがなされるなかで、地形、敷地の形状、風土、独自の空気、気分、そして季節感にいたるまでが建物の細部にまとわりつきはじめる。それを最大限許容していくことに、私の実務的な関心はあるのだが、いいかえると、この過程は、建築に与えられる純枠形態の、変形過程とみるべきかも知れない。
先に、できあがった自分の建築を、あらためて分析してみる、といったのは、この変形過程を、逆にたどって、当初の原型的イメージに、もういちど還元してみる作業をしていることを指している。
〈還元シリーズ〉と名づけたのは、このような作業に由来する。ここではいままで私が設計した公共的、商業的な建物が、順々にとりあげられている。おそらく、ひとつの建物につき、ひとつだけしかつくられないだろうが、そのいずれもが、建物を発想して、決定的なアイディアとして定着していったときのイメージを、そのままの状態で二次元的な平面上に表現するように意図している。だから設計過程で、これとまったく同じものがスケッチされた、というわけではない。近似的なものは、いくつも描かれている。だが最終的な設計図としておさまる過程で、そのスケッチは、変形を加えられている。同時に、建築は三次元的な立体であり、空間を包含しているのだが、設計の段階では、平面や立面や断面といった、切断された二次元的な図だけを扱っていることが多い。その図が描かれているときに、建築家は、常に三次元的な空間として、それが実寸大に拡張されて実現するときの有様を、想像し読みとる訓練がなされていなければならず、そんな背後の意図を断片的に指示する記符号として図を読むわけだから、建築になじみのない人たちには、とりつきにくいものになっている。そこで、原型に還元されたものを、二次元的な面のうえで立体的な像として再現する手段を構じる必要がうまれる。アクソノメトリックと呼ばれる図法を用いると、平面が立体的にみえる。普通は、30°あるいは45°の斜めからみるので、丁度、源氏物語絵巻などにみられるような、日本の伝統的な吹抜屋台の画法に似ている。それをあえて、90°という垂直にみたまんまで、ここでは描いてある。90°にしたアクソノメトリックは、線猫だけではかなり読みとりにくいけど、これに陰影をつけると立体的に立ちあがってくる。シルクスクリーンで刷ることが実は陰影をつけやすくしているのである。つまり、この印刷過程で、画面はすべて色面に分解されねばならない。だから、エッチングなどの線の集合体のややこしさに較べて、陰影を簡単につけることができる。
アクソノメトリックの特徴は、平面図も立面図も変形することなしに、そのまま組込まれてしまっていることである。相互を連結してしまうだけで立体的な表現へ接近できる。そのために近代になって建築家から愛用されている方式である。平面と立面を同時にみせることは、いいかえると、無限大の焦点距離で、空中から建物を視ている状態になる。鳥瞰図的な視点といっていい。問題は、航空写真でも撮らないかぎり、現実にはこれに似た視点で建物がみえることはないので、むしろ、抽象的で、概念的な表現になってしまうことである。源氏物語絵巻の吹抜屋台は、寝殿造りの室内を、屋根をとりはずして眺め下している。それを神の視点だ、という人もある。住吉天神縁起では、たとえば、雷神などがその一隅に出現する。黒雲にのった雷神は空中にあるわけで、そこから室内を見下しているのはいいが、この雷神も同時に上方から見下ろされる。これは、描法の限界といえるかも知れない。もしこの吹抜屋台の描法の比喩を用いるならば、アクソノメトリックは、視線の生み出すヒエラルキーを解体したあげくに、各部分を均質化して、抽象的な空間のなかに浮かしてしまう、神も人間もかかわらない協約的視点といっていい。必然的に土地や風土の制約は捨象され、独立した抽象形態としてのみ描かれることになる。
それ故に、発生状態にあるイメージを定着するのに適した手法と思える。その段階では、建築は、地形の特性も、生活の臭いも、背後のわい雑な電柱や看板もない。純粋な幾何学性をもった空間や、ひとつの形式としての構造体でしかない。その有様だけをシルクスクリーンで定着する。<還元シリーズ>は、そこで、幾何学的な立体、架構体、そしてプライマリーな色彩、それだけに還元された建築の原始形態なのである。<ヴィッラ・シリーズ>は、住宅だけを扱うことにしている。私の住宅では、これまでバレル・ヴォールトがかなり基本的な共通のモチーフになってきている。そして、居住空間も原則的に、立方体や円筒に基いている。<還元シリーズ>では、部分的に輪郭まで分解する作業をしているが、<ヴィッラ・シリーズ>は、むしろ、輪郭を大事にし、そのなかの空間が暗示されるように心がけている。いいかえると、ここでの住宅は、ひとつの彫刻的なオブジェクトとしてみてもいいという表明である。建物を幾何学的形態に基いて構築することは、私のフォルマリスト的なアプローチの原則でもある。このようにしてえらびだされている形態が、独自に展開して、次々に住居の形式を組みたてていくという、運動過程がみえてくれば、いっそう目的が達せられることになる。
今度、新しくはじめたのに<MOCA#1、#2、#3、>のような、普通の透視図法に基いたシルクスクリーンがある。ここでは、ロサンゼルスという、透明な空気と、激しい太陽の下に置かれる美術館として、インド産の赤砂岩を用いたデザインの意図を的確に表現したいと思ったときに、空を導入することがどうしても必要だと考えた。アクソノメトリックの方式でやると、地面を空中から見下すことになって、決して空はあらわれない。そこで、描法を変えて、普通の地上の視点からみた透視図法を用いることにしたのである。建物は、それでも極端に単純化されて、この建物の基本形である純粋立体幾何学のみが浮びあがるようにしてある。そして、色彩と陰影と、空を強調して、ロサンゼルスの空気を表現することを試みたものである。これはいずれ実物として建ちあがるだろう。そのとき写真がとられたとしても、これとは異ってうつるにちがいない。若干の緑が植えられ、既存の建物にとりまかれ、人や車がうごいているだろう。そんななかに置かれる建物の基本的なイメージが、ここでもやはり抽出されようとしている。
版画の利点は、たったひとつのオリジナルという古典的なアウラの痕跡を越えて、複製され、流通することである。勿論私自身、建物の設計過程でスケッチを大量に残すことがある。だけどこれは製図板のうえで、かたちを捜している過程の断片で、決してみせるためにやっているのではない。むしろ必要なのはそのスケッチをスタッフが描きなおし、建築的な図面にすることである。とすれば、手の痕跡だけで勝負するアーティストとは異って、建築家には、手の痕跡は決定的な重要性を持っていないと考えていい。むしろ、私にとって重要なのは、その作業過程にたちあらわれる建築の基本的概念が、どのように伝達され、実施され、具体的な空間となるかという点である。とすれば、そのアイディアがもっとも的確に表現され、伝達される手段がみつかればいいわけで、そのような図法を開発していくことの方がより大きい課題となる。版画は、ここで生まれた図法を再現し、複製にしてくれる。単一のクライアントだけを相手にし、特定の場所に固定される宿命をもつ建築が、ここで複数化し、より多くの人々の眼にふれることになる。その点においても、版画は、閉ざされたアイディアを開放する役割りもしてくれる。仕事の区切りに、版画をつくるという楽しみもまだこれからも残されている、というわけである。
(いそざき あらた)


『The Prints of Arata Isozaki 1977-1983』所収
発行日:1983年11月4日
発行:現代版画センター
執筆:磯崎新、松岡正剛、八束はじめ
英訳:ドナルド・フィリパイ、木幡和江、南谷覺正
デザイン:横尾忠則
編集:星野治樹
シルクスクリーン刷り:石田了一
銅版画刷り:山村兄弟版画工房

磯崎新「FOLLYー草庵」
1983年 シルクスクリーン(刷り:石田了一)
16×19cm
限定1,500部
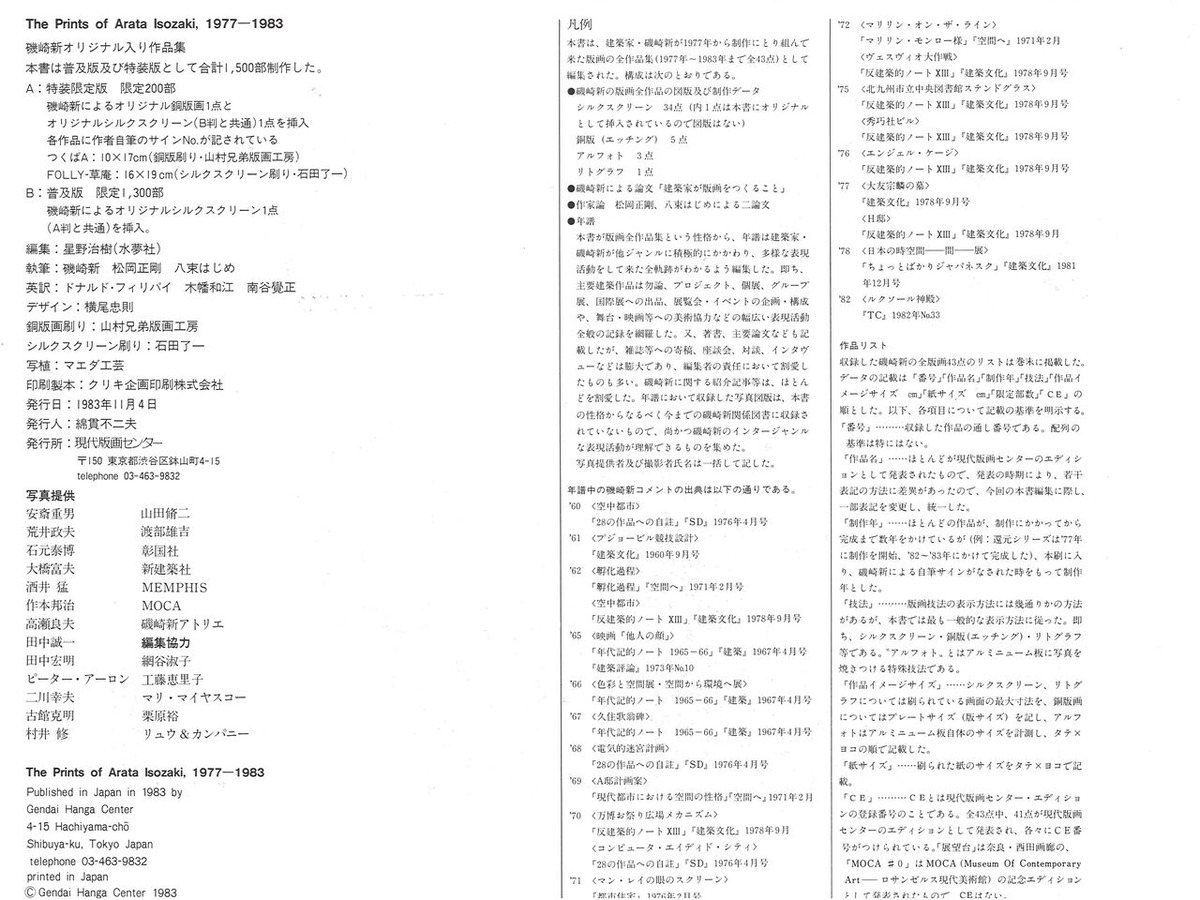 奥付
奥付
コメント