美術展のおこぼれ 12
「大英博物館 古代ギリシャ展 究極の身体、完全なる美」
会期:2011年7月5日(火)~2011年9月25日(日)
会場:国立西洋美術館
「円盤投げ(ディスコボロス)」の彫像1点に特別展示室が与えられ、四方からゆっくり観賞できるようになっている。こうした扱いは最近の企画展でよく見られるもので、絵画でもルネサンス展やゴーギャン展は目玉となる1点を演出していたし、彫像では一昨年の「国宝 阿修羅展」が、阿修羅の周りを幾重にも囲む観客の姿まで取り込んで、どこか宗教的なシーンとさえなっていた。
それで当然思い出すのは、東京オリンピックの1964年、同じ西洋美術館で同じ古代ギリシャの彫像「ミロのヴィーナス」を展示して、記録的な観客動員を呼んだ出来事である。目玉作品どころか、それ1点だけを見るために連日長い列をつくったわけで、そのちょうど10年後の「モナリザ展」のときもすごく(入場者数150万人といわれた)、数字としてはこちらの方が上かも知れないが、「実物を見ること」のそれまでになかった高揚感を日本人が抱いたのはヴィーナス像のほうだという気がする。日本がそういう時代だったとも思うけれど、なんといっても古代ギリシャであり作者名もない。紀元前四世紀のものの前二世紀の模刻といわれるが、その神性とアウラは頂点に達している。それをみんなが見に行ったにちがいない。
つまり「ミロのヴィーナス展」は見た目からしても絶対の「静止」に支えられていた。対して今回の「古代ギリシャ展」では、代表のディスコボロス選手の姿は今日の眼で見れば世俗的なスポーツの一場面とも受けとれてしまうし、この像の模刻(が今回の作品)は紀元後二世紀、しかもかのハドリアヌス・ヴィラにあったものを十八世紀後半、新古典主義隆盛の勢いづくなかで発掘されたのだという。
つまり完成に到達した古代ギリシャ美術を後の時代が延々とコピーしたり収集したりしながら追いかけて、(私たちもその美しさに文句なく魅せられるとすれば)現代にまで至る「動き」を、ほかの展示作品もあわせて伝えようとする企画展なのだ。
子どもの頃、こうした古代ギリシャ彫刻の写真を見て、日本なら弥生時代で素朴な埴輪土器などをつくっているのと同じころに、向こうでは人体の理想と造形美とをあわせてこれ以上ない完璧なものを一気につくってしまった凄さというか、人種の能力の差に愕然とするばかりだったが、今回展のように全体がさまざまな切り口できちんと構成されたなかだと、あらためていろいろな興味が涌いてくる。
理想的な人体イコール神の姿という宗教観は、結果をみればまったく明快だが、その考えの道筋を貫き通すために何を生かし何を排除してきたのか。そもそもその理由として人間を重ね合わすことのできる(男女関係や殺したり盗んだりする点でそうとうヤバイ)ギリシャの神々の元型がどのように確立されたのか。ある意味では異様なのだ。信仰する対象を彫像化しようとするとき、自分とできるだけ遠い存在を表現するのがどうしたって自然である。神仏の表現にあたって人の姿を極力避け、後にギリシャ彫刻の影響もあって人間的な写実に向かうことがあってもそこでは人との距離をさらに深くとろうとする仂きが、多くの文化圏の神仏像表現においては衰えることがなかったんじゃないだろうか。のびやかで動きをはらんでいるディスコボロス青年にはスポーツの原点を感じる。だが土俵上に仁王立ちになった魁皇の魁偉な姿にわたしたちは当然のように、人間を超えた聖なるものの存在を感じ取る。その違いはいまでもある。
今回展には「神話の世界」や「人々の暮らし」といった章もちゃんと用意されて、古代ギリシャの多様性を知ることができるが、サブタイトルにもある「究極の身体、完全なる美」の明快さにやっぱり全体の印象はきわまるだろう。それが思考の明晰さにのみ結びついた結果なのかどうかは会場を一巡しただけではよく分からない。図録を買っていないので、論文・解説ではどこまで言及されているか知らないのだが、逆にいえば「完全なる美」に至らしめた、いわば闇の部分、たとえばE.R.ドッズが解明したギリシャ人の「非理性(The irrational)の領域にも、じつに久しぶりに興味が戻ってきたのだった。
(2011.7.22 うえだまこと)
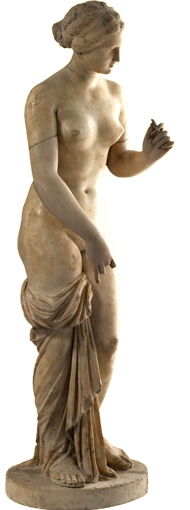 《アフロディテ(ヴィーナス)像》
《アフロディテ(ヴィーナス)像》
ローマ時代(原作:前4世紀) パロス産大理石
高さ107cm|幅33cm|奥行35cm
◆ときの忘れものでは下記の皆さんのエッセイを連載しています。
植田実さんのエッセイは毎月数回、更新は随時行います。
大竹昭子さんのエッセイは毎月15日の更新です。
井桁裕子さんのエッセイは毎月20日の更新です。
山田陽さんのエッセイは毎月30日の更新です。
今までのバックナンバーはコチラをクリックしてください。
「大英博物館 古代ギリシャ展 究極の身体、完全なる美」
会期:2011年7月5日(火)~2011年9月25日(日)
会場:国立西洋美術館
「円盤投げ(ディスコボロス)」の彫像1点に特別展示室が与えられ、四方からゆっくり観賞できるようになっている。こうした扱いは最近の企画展でよく見られるもので、絵画でもルネサンス展やゴーギャン展は目玉となる1点を演出していたし、彫像では一昨年の「国宝 阿修羅展」が、阿修羅の周りを幾重にも囲む観客の姿まで取り込んで、どこか宗教的なシーンとさえなっていた。
それで当然思い出すのは、東京オリンピックの1964年、同じ西洋美術館で同じ古代ギリシャの彫像「ミロのヴィーナス」を展示して、記録的な観客動員を呼んだ出来事である。目玉作品どころか、それ1点だけを見るために連日長い列をつくったわけで、そのちょうど10年後の「モナリザ展」のときもすごく(入場者数150万人といわれた)、数字としてはこちらの方が上かも知れないが、「実物を見ること」のそれまでになかった高揚感を日本人が抱いたのはヴィーナス像のほうだという気がする。日本がそういう時代だったとも思うけれど、なんといっても古代ギリシャであり作者名もない。紀元前四世紀のものの前二世紀の模刻といわれるが、その神性とアウラは頂点に達している。それをみんなが見に行ったにちがいない。
つまり「ミロのヴィーナス展」は見た目からしても絶対の「静止」に支えられていた。対して今回の「古代ギリシャ展」では、代表のディスコボロス選手の姿は今日の眼で見れば世俗的なスポーツの一場面とも受けとれてしまうし、この像の模刻(が今回の作品)は紀元後二世紀、しかもかのハドリアヌス・ヴィラにあったものを十八世紀後半、新古典主義隆盛の勢いづくなかで発掘されたのだという。
つまり完成に到達した古代ギリシャ美術を後の時代が延々とコピーしたり収集したりしながら追いかけて、(私たちもその美しさに文句なく魅せられるとすれば)現代にまで至る「動き」を、ほかの展示作品もあわせて伝えようとする企画展なのだ。
子どもの頃、こうした古代ギリシャ彫刻の写真を見て、日本なら弥生時代で素朴な埴輪土器などをつくっているのと同じころに、向こうでは人体の理想と造形美とをあわせてこれ以上ない完璧なものを一気につくってしまった凄さというか、人種の能力の差に愕然とするばかりだったが、今回展のように全体がさまざまな切り口できちんと構成されたなかだと、あらためていろいろな興味が涌いてくる。
理想的な人体イコール神の姿という宗教観は、結果をみればまったく明快だが、その考えの道筋を貫き通すために何を生かし何を排除してきたのか。そもそもその理由として人間を重ね合わすことのできる(男女関係や殺したり盗んだりする点でそうとうヤバイ)ギリシャの神々の元型がどのように確立されたのか。ある意味では異様なのだ。信仰する対象を彫像化しようとするとき、自分とできるだけ遠い存在を表現するのがどうしたって自然である。神仏の表現にあたって人の姿を極力避け、後にギリシャ彫刻の影響もあって人間的な写実に向かうことがあってもそこでは人との距離をさらに深くとろうとする仂きが、多くの文化圏の神仏像表現においては衰えることがなかったんじゃないだろうか。のびやかで動きをはらんでいるディスコボロス青年にはスポーツの原点を感じる。だが土俵上に仁王立ちになった魁皇の魁偉な姿にわたしたちは当然のように、人間を超えた聖なるものの存在を感じ取る。その違いはいまでもある。
今回展には「神話の世界」や「人々の暮らし」といった章もちゃんと用意されて、古代ギリシャの多様性を知ることができるが、サブタイトルにもある「究極の身体、完全なる美」の明快さにやっぱり全体の印象はきわまるだろう。それが思考の明晰さにのみ結びついた結果なのかどうかは会場を一巡しただけではよく分からない。図録を買っていないので、論文・解説ではどこまで言及されているか知らないのだが、逆にいえば「完全なる美」に至らしめた、いわば闇の部分、たとえばE.R.ドッズが解明したギリシャ人の「非理性(The irrational)の領域にも、じつに久しぶりに興味が戻ってきたのだった。
(2011.7.22 うえだまこと)
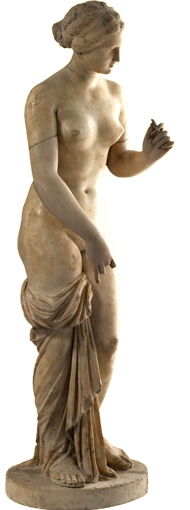 《アフロディテ(ヴィーナス)像》
《アフロディテ(ヴィーナス)像》ローマ時代(原作:前4世紀) パロス産大理石
高さ107cm|幅33cm|奥行35cm
◆ときの忘れものでは下記の皆さんのエッセイを連載しています。
植田実さんのエッセイは毎月数回、更新は随時行います。
大竹昭子さんのエッセイは毎月15日の更新です。
井桁裕子さんのエッセイは毎月20日の更新です。
山田陽さんのエッセイは毎月30日の更新です。
今までのバックナンバーはコチラをクリックしてください。
コメント